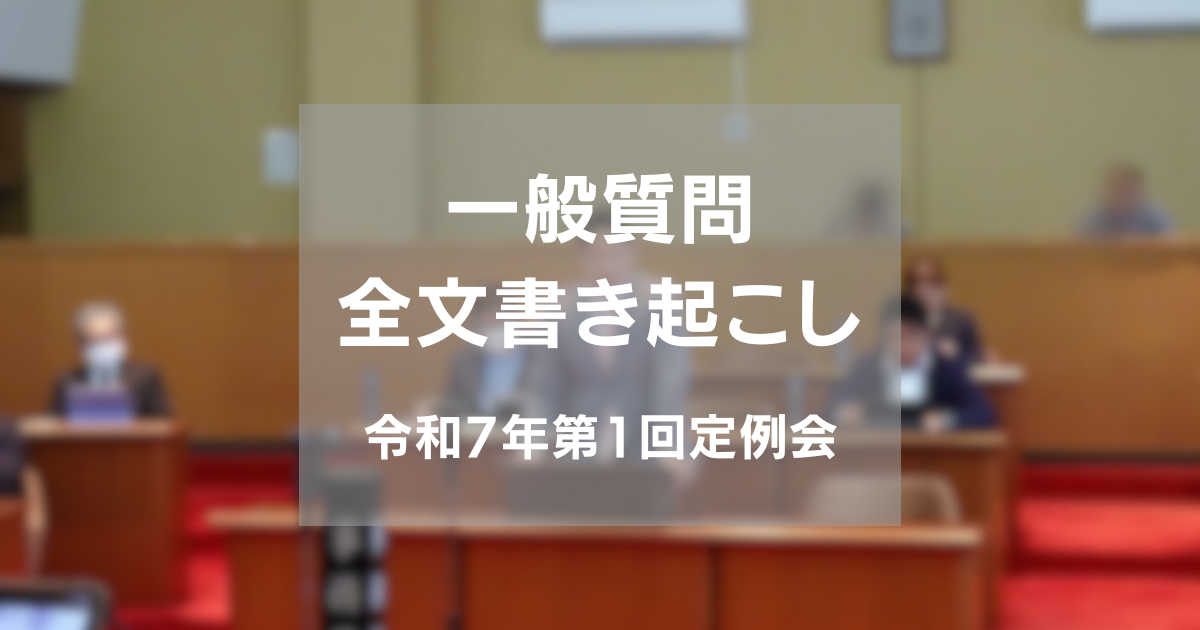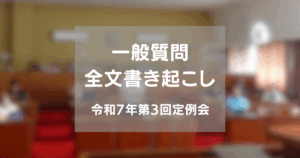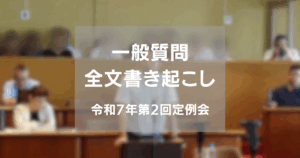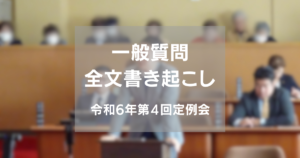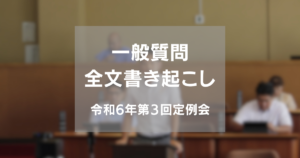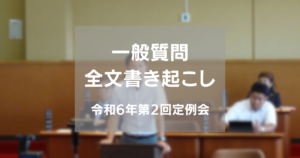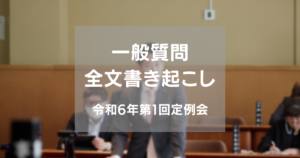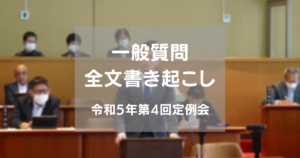令和7年第1回定例会のうち、3月4日に行われた一般質問について、私が書き起こした全文をアップします。
一般質問については、以前の投稿(初めての一般質問を終えて)で概要をご説明しておりますので、よろしければご覧ください。
※展開がわかりやすいように、吹き出し風に文章を適宜挿入します。
※行政からの答弁については、青い囲み文字で記します。
※議場での発言には議長の許可が必要なので、実際には議員、職員ともに発言ごとに挙手→議長からの許可の流れがありますが、ここでは便宜的に省略します。
「一般質問なんて聞いたことがない」
「聞いていてもつまらない」
そんな感想をお持ちの方も少なくないと思います。
私としてもそのお気持ちがよくわかるので、手元に資料がなくても話の流れがつかみやすいように、構成や原稿は頑張って工夫しております。
議員となってから8回目の一般質問となりました。
毎回成長を実感していただけるような質問にしたいと思って取り組んでいますが、ご意見等いただけるとありがたく思います。
ご興味のあるカテゴリだけでも、拾い読みしてもらえたら幸いです。
※発言の内容は下記の通告書通りになります。
1.エビデンスに基づく政策立案について
(1)EBPMについての認識
2.若年層の移住・定住政策について
(1)子育て支援事業の拡充
(2)働く場としてのアプローチ
(3)子育て賃貸住宅の運営状況
(4)個別事業の現状と課題
※クリックすると該当部分にジャンプします(画面右下の矢印ボタンで最上部に戻れます)
下記の文章はあくまで私がYoutubeでのアーカイブ配信を個人的に書き起こしたものであり、正式な議事録ではありませんのでご了承ください。
議事録がアップされましたらこちらにそのリンクを追記する予定です。
↓↓↓↓↓↓↓↓
【追記】議事録が公開されたため、下記にリンクを記載します。
※令和7年第1回定例会→第1号 3月4日の順にクリックで閲覧できます。
以下発言

おはようございます。無所属の石﨑です。
ただいま議長から発言の許可を頂きましたので、一問一答方式で質問を行わせていただきます。
内容につきましては発言通告書どおり、エビデンスに基づく政策立案について、そして若年層の移住・定住政策についての2点となります。
よろしくお願いします。
エビデンスに基づく政策立案について

早速質問に入ってまいります。
1番、エビデンスに基づく政策立案についてです。
少し抽象的なテーマになってしまうため、前段として、この概念について説明をさせていただきます。
現在行政運営においては、このエビデンスに基づく政策立案という考え方が重要視されてきています。
英訳するとエビデンス・ベースド・ポリシー・メーキング、頭文字を取ってEBPMと呼ばれることが多い概念です。
これは統計データや客観的な証拠を基に政策を立案し、その効果を検証しながら行政運営を行う手法です。
従来の政策決定は、過去の慣習や経験則、あるいは主観的な判断に基づくことが少なくありませんでした。
しかし財政が厳しく人口減少が進む昨今の状況下においては、限られた資源を最大限に活用し、より効果的な施策を実行することが求められます。
そのためには、政策の根拠となるデータを収集・分析し、それを基に意思決定を行うEBPMの考え方が必要不可欠となってきます。
日本においてEBPMが本格的に注目され始めたのは、平成29年頃です。
同年5月に開催された経済財政諮問会議においてEBPMの推進が重要課題として取り上げられ、政策の効果を客観的に測定し、明確な根拠や証拠に基づいて政策決定を行うことが政府の方針として打ち出されました。
その後、平成30年6月の経済財政運営と改革の基本方針では、EBPMの本格的な推進が正式に位置づけられました。
そして令和元年4月には、EBPM推進のためのガイドラインが内閣府から公表され、各省庁や地方自治体においてEBPMを導入、実践するための指針が示されました。
これに伴い、令和2年以降、各省庁や地方自治体でEBPMの活用が進められ、国の政策評価の基準として定着しつつあります。
特に昨今、行政の効率化や政策のPDCAサイクルの強化、財政の最適配分といった観点からEBPMの重要性が再認識されています。
こうした中で、数多くの課題を抱える本市においてもEBPMを導入し、政策立案の精度を高め、効果を最大化していくことが求められていると考えます。
ここで(1)のEBPMについての市の認識に入りますが、今説明したEBPMの手法について、どのような認識を持っているのか伺います。
議員おっしゃるように、限られた資源の中で政策の効果を最大限発揮させるために、近年EBPM政策をプロセス意識的に取り入れながら行政運営を行っていくことが求められており、国の省庁や神奈川県横須賀市などにおいては、推進の取り組みが始まっているものと認識しております。
隣の横須賀市はEBPMの導入にいち早く取り組み、総務省が平成30年に実施した第3回地方公共団体における統計利活用表彰において、『横須賀市のEBPM推進に寄与する経済波及効果分析ツールの開発と全庁的活用』が、最上位の賞となる総務大臣賞を受賞したと聞き及んでおります。
かけられる予算や人的配置が異なるとしても、EBPMの推進はそう遠い話ではないということが言えると思います。
政策立案のパターンにはさまざまなケースがあると思いますが、一般論として、本市における政策立案が現状どのようなプロセスで行われているのかをお聞かせください。
政策の分野や性質によっても異なりますが、一般的には政策課題を認識するところから始まりまして、課題に関連する情報収集の上、原因を把握し課題解消のための手法を検討するというプロセスを経て、政策立案に至っております。
政策立案のプロセスについては、課題の認識、情報の収集、原因の把握、解決手法の検討という流れを経て実施されているとのことです。
当然ながら、こうした政策立案の過程では、原因分析や仮説の検証を踏まえた上で、一定の合理性に基づいた意思決定がなされているものと理解をしています。
しかしながら、現代の行政運営においては、より客観的かつ体系的な手法によって政策の妥当性や効果を検証し、より精度の高い意思決定を行うことが求められています。
そのための有効なアプローチの一つが、ロジックモデルの活用です。
ロジックモデルとは、政策が目指す目標とその達成プロセスを明確にし、因果関係を整理するための手法です。
少し話が込み入ってしまうので概要の説明にとどめますけれども、要はそれぞれのフェーズにおける政策の構造を可視化し、施策がどのように目的達成へと結びつくのかを明確にするものです。
国や他の自治体でもEBPMの推進に当たりロジックモデルを導入する動きが進んでいますが、本市においてもこのような手法を政策立案の過程に取り入れているのか、また導入の可能性についてどのように考えているのか伺います。
ロジックモデルでございますが、ポイントの一つに政策の体系化がございます。
本市の実施計画体系は4層のピラミッド構造となっております。
上から順に、数値目標を定めた政策分野ごとの基本目標、基本目標を達成するために講ずべき施策の基本的方向、各施策の効果を客観的に検証できるようにするために重要業績評価指標、KPIでございますが、これを定めた具体的施策、そして事務事業です。
この体系は、下位の階層が上位の階層の目的を達成するための手段という関係性であるとともに、政策がどのような目的の下にどのような手段を用いるものなのかという対応関係を示すものとなっており、政策の体系化ができております。
さらに新規の実施計画事業の立案や重点施策等の評価結果を踏まえた実施計画事業の見直しの際には、実施計画に定める基本目標ごとの数値目標及び基本的方向ごとのKPI達成に資するような事業を立案することとしております。
EBPMにおけるロジックモデルのように、因果関係が明確に図式化されているわけではございませんが、ロジックモデルの考え方が一定程度踏まえられ、政策立案を行っているということになっております。
本市において、政策のピラミッド構造を通じた体系化が行われていることは理解をしました。
考え方によっては、広義の意味でロジックモデルを踏まえていると言えるのかもしれません。
しかし、ロジックモデルの本来の意義は単なる政策の体系化や整理ではなくて、施策と成果の因果関係を明確にし科学的根拠に基づく政策判断を可能にすることです。
先ほどの答弁では、政策の基本目標から具体的施策へと階層的に整理されているとのことですが、これはロジックモデルの構造化の部分を満たしているだけであり、因果関係の明確化までには至っていないのではないかなと感じます。
もちろんこの因果関係の明確化についても、部署や担当者によっては意識的に、あるいは無意識的に行っているのかもしれません。
しかし、いずれにせよ政策立案において全庁的なロジックモデルの可視化や仕組み化には至っていないのが現状かなと思います。

さて、EBPMの認識を確認したところで、(2)庁内における統計データの運用に移ります。
EBPMを実践する上で、統計データの活用は政策立案の段階において不可欠となってきます。
適切な政策を立案するためには現状の課題を正確に把握し、データに基づいて施策の方向性を決定することが求められるからです。
そこでまず、本市における統計データの運用体制を確認していきたいと思います。
本市では、統計データの管理や活用をどの部署が所轄し、どのような業務を担っているのかお聞かせください。
統計データの運用につきましては、デジタル課が所管課となっております。
業務としましては国・県から委託された統計調査の実施や、三浦市の人口・世帯を推計した三浦市統計月報等の作成を行うとともに、広く活用していただくために庁内への周知やホームページでの配信を行っております。
統計データの運用はデジタル課が担っているとのことですが、どのような経緯からデジタル課が所轄課となったのかを伺います。
平成16年4月の機構改革におきまして、情報に係る事務の集約を図ることを目的としまして、当時企画政策関連の業務及び統計業務を所管しておりました行政管理部企画課と、電子計算組織システムの関連業務を所管しておりました行政管理部情報課が統合され、行政管理部企画情報課となりました。
また平成18年4月の機構改革では、企画情報課が所管をしておりました業務のうち、企画政策関連業務は政策経営部政策経営課が所管することとなり、統計業務と電子計算組織システム関連業務は行政情報の管理及び情報政策を推進する課でございます統計情報課が所管することとなりました。
さらに令和3年4月の機構改革におきまして、統計情報をより政策部所掌業務に活用するとともにデジタル化による業務改善を効果的に推進するため、当時市民部に置かれておりました統計情報課が政策部デジタル課となり、現在の形になっております。
統計情報を政策部の所轄業務に取り込む意図で組織改編を行ったことは、結果的にEBPMの推進という側面でも理にかなった判断なのかなと思います。
基本的に各課の担当者は直接国や県の資料、データを調べて政策に生かしているのだと思いますが、もし担当者レベルで求めるデータを得られなかった場合、依頼に応じてデジタル課がデータの提供や分析を行うようなことはあるのか伺います。
各課等の依頼に基づきまして、住民基本台帳データからデータを抽出し提供することは行っておりますが、各課等の事業実施に必要な部分を抽出し提供するだけであり、統計データの分析までは行っていない状況でございます。
現状では、各課の依頼に応じた一部のデータ提供は行われているものの、統計データの分析や政策立案を積極的に支援する専門チームや担当課の設置には至っていないということです。
EBPMを本格的に推進するためには、単にデータを収集・提供するだけではなく、政策の方向性を定める上で必要なデータの整理、分析を行い、各課がより効率的に活用できるよう支援する仕組みが不可欠です。
国や県のデータ、住民基本台帳データ、各種統計情報を統合的に管理し、政策部門と連携しながらデータを活用する横断的な機能も必要なのではないでしょうか。
専門的な支援組織の設置も含め、今後の対応として検討すべきだと考えます。前向きな検討をお願いしたいと思います。
さて、デジタル化の業務としては庁内のDX推進も重要なミッションであります。
三浦市デジタルトランスフォーメーション推進計画も策定から4年ほどが経過しまして、来年度が計画の最終年度となります。
平成28年12月に施行された官民データ活用推進基本法ではデータの利活用の推進が求められていますが、三浦市デジタルトランスフォーメーション推進計画にはデータの活用についての取り組みが盛り込まれているのか伺います。
現計画の位置づけといたしましては、官民データ活用推進基本法第9条第3項に規定します市町村官民データ活用推進計画の位置づけになっておりますが、個別の取り組みとしましては、データ活用についての取り組みは組み込まれていないのが現状でございます。
どちらかと言えばこの計画は市民サービスの向上やデジタル化による働き方改革、コストカットに主眼が置かれている印象であり、それ自体は非常に重要な取り組みであると考えています。
しかしながら今後の行政運営においては、単なる業務効率化にとどまらずデータの利活用を通じて政策の精度を高める視点も欠かせません。
そのためにはデータ活用推進に関する中長期的なビジョンの設定も必要になると考えますので、ここに提言させていただきます。
さてデータの活用という点では、近年、官民を問わずビッグデータの重要性が高まってきています。
ビッグデータとは、従来のデータ処理技術では扱い切れないほどの膨大な量のデータを指し、これを解析することで社会の動向や行動パターンを可視化し、より精度の高い意思決定を可能にするものです。
例えばスマートシティの実現に向けた交通データの分析や観光・防災分野におけるリアルタイムデータの活用など、自治体においても幅広い分野での活用が進められています。
本市においても、こうしたビッグデータを政策立案や事業運営に活用する可能性があると考えますが、これまで市の事業においてビッグデータを活用した事例があるのか伺います。
市が行った事業ではありませんが、平成27年度に国土交通省により三浦市におけるICT活用観光ビッグデータ社会実験が行われました。
三浦市を訪れる観光客の回遊動線などを確認するための社会実験であり、携帯端末の位置情報を、ビッグデータを活用することで従来把握・予測が困難であった観光客の観光動態について把握し、分析を試みた事例がございます。
国が実施主体ではあるものの、本市の観光動態分析においてビッグデータが活用された事例があるとのことです。
実際にこの社会実験を受けて、当時市としてはどのような認識を持ったのかお聞かせください。
当時実施されたビッグデータ社会実験の効果を受けて、観光案内マップや観光協会のウェブサイトの刷新、強化を図るなど、観光客に対する情報提供のさらなる強化が必要であること、また三浦レンタルサイクル運営協議会によるレンタルサイクルの拡大強化により、自動車やバスを使わない観光提案を強化することが必要であるとの認識を持ちました。
まさに客観的なデータを基に仮説を打ち立て政策立案を検証するという、EBPMの入り口の部分に触れられた事例なのだと思います。
本市において今後EBPMを推進する上でも、国から下りてくるデータだけではなくて民間も含めた膨大なビッグデータを施策展開のために活用していくべきだと考えます。
この点について、現在市として何か行っている取り組みがあるのか伺います。
現在神奈川県観光協会が民間の人流データに係るビッグデータサービスを導入しており、三浦市観光協会においてもそのデータを参照、活用できることとなっております。
市としてもビッグデータを観光施策の企画や実績の検証におけるエビデンスの一つとして活用できると考えており、今後観光協会からデータの提供を受け、またさまざまなデータの収集を行い活用を図ってまいりたいと考えております。
観光の領域では活用の余地があること、そしてそれらを活用していきたいという前向きな答弁を頂きました。
ビッグデータは福祉や防災といった他の政策領域においても重要な要素となると思いますので、ぜひとも全庁的な活用を図ってほしいと思います。
さて、私は前々回の一般質問において、本市における行政評価の実施状況について取り上げました。市政運営におけるPDCAのC、チェックの部分を尋ねたわけですが、今回の質問は政策立案というP、プランの部分に焦点を当てていることになります。
しかし、結果的に政策立案時にこれまで議論してきたEBPMやロジックモデルの手法を用いることで、チェックの部分、すなわち行政評価の精度もより高まるものだと考えられます。
この部分について市としてどのような認識を持っているのかお願いします。
議員おっしゃるように、EBPMという考え方が政策立案のプロセスに組み込まれることで、行政評価における検証の精度をより高めることができるものと考えております。
他方、EBPMの推進のためには多様なデータの利活用を積極的に行っていくことが重要だと認識しておりますが、現状統計データなど客観的な指標の活用や分析のための仕組みが構築されておらず、またその構築のためには体制的にも課題があると考えております。
ロジックモデルを採用することで政策が目指す目標とその達成プロセスが明確になり、庁内や議会におけるチェックが行いやすくなるだけではなく、市民に対しても政策の構造をより分かりやすく伝えられるというメリットが生まれるはずです。
しかし今の答弁にもあったように、EBPMの手法を標準的なものとして定着させるためには依然として体制面での課題が残されているということです。
統計データの活用や分析の仕組みを構築するにあたり、まずは専門的な知見を取り入れることが有効ではないかと考えますが、この点についてどのようにお考えか伺います。
議員おっしゃいますとおり、統計データの活用や分析の仕組みを構築するためには職員だけでの作業は困難でございます。
専門的な知見を有する方々の力を活用する必要があるものと考えております。
新たな人材の登用や委託など、取り組みのやり方というのはいろいろ考えられると思いますので検討をお願いします。
EBPMの手法を取り入れるためには専門的な知見の活用に加え、実際に政策を立案したりデータを駆使する市職員全体のスキル向上も不可欠になるかと思いますが、EBPMやデータ分析に関する研修は実施されているのかお聞かせください。
EBPMやデータ分析につきましての庁内での研修等は、現在は行われておりません。
統計データの活用環境の整備や人材育成も含め、EBPMの推進に向けては、先進自治体での取り組み等も参考にしつつ、研究していきたいという風に考えております。
本市においてEBPMを推進することは、少数精鋭の職員体制の下で市民サービスの質を維持・向上させるために必要不可欠な取り組みだと考えます。
限られた財源や人員の中でより効果的な政策立案を行うには、従来の経験則や主観的な判断に依存せずデータに基づく合理的な意思決定を行うことが求められるからです。
また、EBPMは決して一部の大都市や財源に余裕のある自治体だけが取り組むべきものではありません。
実際に石川県羽咋市、三重県明和町、島根県江津市など、人口5万人未満の自治体でもデータ分析を活用した政策立案に取り組んでいる自治体は少なくありません。
むしろ財政状況の厳しい小規模な自治体にこそ求められる取り組みであるとも考えられます。
今回の答弁を通じ、本市においてもEBPMの重要性が認識されていることが確認できましたが、体制の整備や人材育成の面では依然として課題が残されていると感じています。
いずれにせよ今後専門的な知見の活用や職員の研修機会の確保を含めて、EBPMの実践に向けた具体的な取り組みを進める必要があると考えます。
他の先進自治体の動きを参考にしながら、今後の行政運営の中で積極的に検討していただきたいと思います。
若年層の移住・定住政策について

さて、次のテーマである若年層の移住・定住政策に移ります。
私は以前の一般質問において、本市の少子化の現状と今後の見通しについて取り上げました。
その中で確認されたのは、若年層の人口の数、有配偶率、合計特殊出生率の現状や推移から、本市の少子化の状況は極めて深刻なものであるという現実です。
この状況は決して本市だけの問題ではなく、全国的に少子化が加速する中で今後も人口減少の流れが続くことは避けられません。
そうした中、各自治体が若年層の取り込みをめぐって過度な競争を繰り広げている現状には、私は必ずしも肯定的ではありません。
全国的に国全体の人口が減っている以上、自治体間で限られたパイを奪い合ったとしても持続可能な解決にはならず、本来は国としての抜本的な対策が求められる領域だと考えています。
しかし、だからといってこの現状に指をくわえて待っているわけにはいきません。
本市においても子育て世代をはじめとする若年層が定住しやすい環境を整え地域の魅力を高めることは、少子化対策の一環としてだけではなく、地域の活力を維持するために不可欠な視点です。そこで今回は本市の若年層の移住・定住政策という大きなテーマを掲げながら、私なりの切り口でそれぞれの政策領域に対する質問を展開してまいります。

まず初めに(1)子育て支援事業の拡充についてです。
若年層が移住先を考えるとき最重要視されるのは、自分のこども、将来的に生まれるであろうこどもも含めて、行政がどれだけ手厚い支援を用意しているかという観点であることは容易に想像ができると思います。
これまでもこの子育て支援についてはしつこいぐらい質問や要望を投げかけておりましたが、それらの進捗確認という意味も含めて質問させていただきます。
まず初めに本市の直近の出生数について、推移と令和6年度の見込みを伺います。
本市の出生数は、令和3年度は147人、令和4年度は137人、令和5年度は120人であり減少傾向となっております。
令和7年度の出生数の見込みについては、令和6年1月までの出生数及び妊娠届出書の令和7年2月と3月に出産を予定している妊婦の人数から、令和5年度と同程度と見込んでおります。
直近の数値を伺っても結構な減少傾向でありますが、今年度は何とかとどまってほしいと願うばかりです。
さて、本市の子育て環境の弱みとして市内で分娩が行えない点が挙げられます。
妊産婦の移動支援策として妊産婦タクシー券が交付されており、この部分は何度も確認しているところではありますが、改めて利用状況や市民のニーズ把握、検証について進捗をお伺いします。
妊産婦タクシー券の利用状況は、令和4年度は2,840枚交付し1,044枚の利用があり、利用率は36.8%となっております。
令和5年度は2,840枚交付し1,159枚の利用があり、利用率は40.8%となりました。
なお、令和6年度は9月末現在で1,240枚交付し509件の利用があり、利用率は41%で令和5年度同時期の利用率とほぼ同様となっております。
また令和6年9月から、乳幼児健診において利用の有無や利用目的等を調査項目とした妊産婦タクシー券利用状況アンケートを実施しており、市民ニーズの把握に努めているところでございます。
現在集計中ではございますが、令和7年1月末現在で利用率は65.5%であり、利用目的は妊産婦健診やこどものための医療機関受診が最も多く48.3%を占めております。
本事業の案内は妊娠届出時や赤ちゃん訪問などで行っており、引き続き利用率の向上のため丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
昨年9月から新たにニーズ把握の調査に動き始めたという点は評価したいと思います。
まだ集計期間は短いものの、参考値として半数近くがお母さん本人の健診やこどものための医療機関受診に使われているということが確認できました。
先ほどEBPMというテーマを取り上げましたが、まさにこの妊産婦の移動支援という領域はEBPMの手法によって立案されるべきものだと思います。
この妊産婦タクシー券の交付という施策は、妊産婦の通院支援という側面だけではなくて、子育てに対するトータルでの経済的な負担軽減、そして健やかな出産の支援という政策の目的というものに少し幅を持たせているという認識でおります。
逆に言えば、ロジックモデルで考えた際に妊産婦の移動支援という長期的な成果、いわゆるアウトカムの設定にピンポイントに対応する施策は構築できていないというのも現実かと思います。
ここについては引き続き具体的な支援策を検討していってほしいと思います。
次に、紙おむつ等育児用品支給事業についてです。
こちらは市内の子育て世帯を応援するため、0歳児のお子さんを養育する世帯に対し、商品カタログで選べる紙おむつ等の育児用品をお子様1人につき1回上限1万円まで支給するという本市の独自施策です。
本事業の注文方法は事業者窓口への電話、注文用紙の郵送、オンライン注文と多様です。直近の注文状況や、利便性が高いオンライン注文の利用状況についてお伺いします。
令和5年度については支給決定が118件であり、注文は96件で81.4%の割合でございました。
このうちオンラインでの発注状況は42.7%であり、電話や発注用紙の郵送といったほかの注文方法も活用していただいていると認識しております。
オンラインでの注文状況が4割を超えているとのことで、やはりネットで完結する申請の手続は本事業に関わらずこの世代のニーズに適しているんだと思います。
続いて産後ケア事業についてです。
産後ケア事業は出産後の母子に対して心身のケアや育児サポート等が行われる有意義な事業であり、ニーズが高いと認識をしています。
以前の質問の中でもここについての課題感を確認してきましたが、この事業をよりよいものにするよう検討していることがあるかを伺います。
産後ケア事業でニーズが多い助産師や保健師等による訪問型サービスについては、令和4年度は20件、令和5年度は51件と増加傾向となっております。
そのため希望のあるタイミングでの支援が困難となる可能性があり、現行の直営によるサービスから業務委託によるサービスに変更して実施する予定でございます。
また、これまで利用がなかった宿泊型サービスについては今年度に入り2件の利用がございましたが、利用者が利用しやすいよう補助金を有効活用し自己負担額を軽減できるよう検討しているところでございます。
訪問型サービスについては直営であることがある種の強みであったと認識していますが、増加するニーズに対応するためには業務委託という形を取ることも必要な対応であると考えます。
引き続き要望した妊産婦の方々がこれまでどおり安心してサービスを受けられるよう、適切な事業者選定をお願いします。
宿泊型サービスについては、ようやく利用実績が出てきたとのことです。
以前から自己負担額の軽減を要望しておりましたが、その部分も着手を検討しているとのことでうれしく思います。
さて、次に乳幼児期の保育環境についてです。現在、三浦市の待機児童及び保留児童の状況はどうなっているのかお聞かせください。
令和6年4月1日現在で待機児童はゼロ人、保留児童は26人となっております。
令和7年4月入所の状況については既に選考が終了している時期かと思いますが、申込み人数と入所の状況がどうなっているのかお尋ねします。
令和7年4月入所希望の申請者数は93人となっております。
このうち59人に対し入所の決定がなされております。なお、入所決定に至らなかった人数は34人となっております。
待機児童ではなく、あくまで希望する保育園に入れなかった保留児童の部分であったとしても、入所希望者のうち約3人に1人が入所できないという状況はなかなか厳しい数値だと思います。
内訳としてどのような偏在があるのか、入所保留となった乳幼児の保護者が希望している保育園ごとの人数についてお聞かせください。
複数の利用希望が出ている申請者もいらっしゃるため、第1希望の保育園ごとの人数をお答えいたします。
上宮田小羊保育園が25人、二葉保育園が7人、初声保育園が2人となっております。
上宮田小羊保育園への入所希望が集中している状況でございます。
上宮田小羊保育園への偏在がすさまじいことが分かりました。
子育て賃貸住宅の供用開始、新しいマンションの建設などでこの偏在状況はより強まっていくことも予想されます。
エリアを問わず、これからの保留児童の解消のために市としてどのように取り組んでいくつもりなのかお聞かせください。
やはり小羊保育園さんが駅に近いということで、希望が多いという実態があります。
保留児童の解消のためには、保育園における児童の受入れ数を増やすためには十分な数の保育士を確保する必要があります。
また、国の方針として保育施設における量から質への転換が示されていることから、一層の保育の質の向上のためにも保育士の確保というものは大変重要であると考えております。
令和6年度より保育士への家賃を補助する事業を開始するなど、保育士の確保のために取り組んでいるところでございます。
さらに令和7年度からは、三浦海岸駅前にて新たに実施する予定の一時預かり事業においても、保育ニーズの高いお子さんを定期的に預かることができる仕組みを検討しております。
保留児童となった場合の受皿としての機能も、一部果たせるものと考えております。
確かに保育の質の向上という観点はもちろん、保育士の業務負担の軽減、ひいては保育園の持続可能な運営という観点からも保育士の確保は極めて重要です。
また来年度に新たに実施が検討されている一時預かり事業についても、保育園だけでは賄い切れない保育ニーズに対応する現実的な施策として有効性があると考えます。
このあたりの詳細は後日行われる予算審査で見てしっかり確認させていただきますが、市としても保育施策の充実に向けて積極的に対応を進めていることが確認できました。
私自身、現在2人の乳幼児を育てている立場であります。
今回は施策の進捗確認という側面が中心でしたが、市内に住む子育て世代の代弁者として今後も実態に即した提言を行ってまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

さて、次の項目である働く場としてのアプローチに移ります。
若年層の移住・定住を考える上でもう一つ重要になるのが、働く場としての三浦という視点です。
本市は都心への通勤圏としてのベッドタウン機能を担い、人口を増やしてきた歴史があります。
しかし近年はテレワークの普及や都心回帰の傾向が進み、もはやベッドタウンとしての魅力だけで流入人口を増やすことは難しくなってきています。
以前の私の質問でも確認しましたが、三浦市はここ数年転入より転出が多い社会減の状態が続いており、特に若年層の流出が顕著です。
これは単に住環境のよさだけでは移住・定住の決め手にはならないという現実を示しています。
一方で、雇用を生む企業誘致は即効性のある施策として効果的ですが、立地条件やインフラ、企業側のニーズなどさまざまな課題があり一筋縄ではいかないのが実情です。
こうした課題を踏まえれば、三浦において働くことを前提とした移住・定住を促進するためには、既存のベッドタウン機能に頼るだけではなく、『どのような働き方であれば三浦での暮らしと両立ができるのかという視点を明確にすること』が重要です。
三浦市には、豊かな自然環境や都市部にはないゆとりがある暮らしが可能な住環境という強みがあります。
これらを生かし、三浦に住みながら働くという若年層のペルソナを明確に設定し、行政として彼らの移住・定住ニーズに応えていくことが必要だと考えます。
この前提に立って質問をしますが、まず考えられるのが三浦で起業し事業主として働くという選択肢です。本市としても起業・創業の支援を行っていると認識をしていますが、具体的にどのような枠組みで実施をされているのか伺います。
中小企業の活力の再生などを定めた産業競争力強化法に基づき、平成28年5月に創業支援等事業計画の認定を受け、必要な施策を実施しております。
ただいまの答弁に創業支援等事業計画というものが出てきましたが、どのようなものなのかお聞かせください。
市は創業の相談窓口となり、国・県・市の創業支援事業を紹介するとともに、相談内容や事業者の各ステージに応じ、三浦商工会議所や地域金融機関、公益財団法人神奈川産業振興センターや三浦半島地域活性化協議会を紹介し、連携して支援を行うこととしております。
主たる支援施策等は、特定創業支援等事業として創業を希望する者に経営、財務、人材育成、販路拡大などの基本的な知識の習得を促す講座を三浦商工会議所などの支援機関が実施しております。
市はこの講座を受講し、全ての知識を習得した者に対して証明書を発行することとなっております。
この証明書を受けた者は、登録免許税の軽減など優遇措置が受けられるようになります。
起業・創業に必要な知識の習得に加え、受講者に対しての優遇措置も用意しているとのことです。
直近でこちらの受講証明書は何件くらい発行されているのかを伺います。
近年の発行件数は、令和3年度は2件、令和4年度は14件、令和5年度は11件、令和6年度は1月末までで7件の証明書を発行しております。
直近の4年間で34件の証明書を発行しているとのことです。
申請者の年齢や希望している職種には、どのような傾向があるのかお聞かせください。
申請者の申請時の年代は、30代が10人、40代が13人、50代が8人、60代が3人となりました。
また創業を目指す職種はおよそ3分の1が飲食関係で、その他は小売業や介護事業などさまざまな事業となっております。
申請者の7割近くが30代、40代ということで、創業支援は若年層へのアプローチという意味でも重要な施策となるのかなと思います。
参考までに、市の制度で行われる創業支援にはほかにどのようなものがあるのか伺います。
市の制度における創業支援策のうち主な事業としては神奈川県の制度融資で、創業支援融資を受けた際、支払った信用保証料の2分の1以内、5万円を上限に補助を行っております。
また三浦商工会議所と共催で創業の基本を学べる創業支援セミナーを毎年1回開催しております。
さらに横須賀市京浜急行電鉄と共催で、事業承継を含め新しいことを始めようとする方を対象に、ワークショップ形式で起業・創業の生きたノウハウをお伝えする新規事業開発セミナーを開催しております。
市の取り組みについて理解をしました。
起業・創業ということであれば、事業を立ち上げるだけではなくて事業を継続していくための支援、すなわち起業後のフォローや仲間づくりも重要になってくると考えられます。
こうした観点も踏まえて今後創業支援をどのように進めていくつもりであるのかを伺います。
市の担当職員では、事業内容の改善点や収支、資金繰りなどの具体的な相談に応じることの難しさがあると認識しております。
そのため事業内容や事業計画であれば商工会議所や神奈川産業振興センターに、事業収支や資金繰りであれば金融機関にといった、相談のニーズを的確に把握し民間支援事業者と連携することが重要であると考えております。
一方で企業、個人事業主などさまざまな担い手が連携・協働していくことが事業の継続、地域の活性化には必要であると認識しております。
現状では、相談者から要望があった際は適宜地元のイベントや団体の紹介、マッチングを個々のケースに応じて実施しております。
今後はこのような丁寧な対応をマニュアル化するなど整備を行い、創業者の各ステージに応じた支援策を行うことが重要であると考えております。
今答弁にもあったように、本市で起業してくださる方との連携や協働というのは地域の活性化にも寄与するものであり、その意味でも起業・創業支援というのは市民全体のための政策として意義のあるものだと思います。
さらなる支援体制の強化をお願いします。
さて、本市での新しい働き方のもう一つの観点としてリモートワークがあります。
リモートワークとは、インターネット環境を活用しオフィス以外の場所で業務を行う働き方のことを指します。
近年のデジタル化の進展や働き方改革の影響により出社を前提としない雇用形態が広がりつつあり、都心の企業に所属しながらも自宅やコワーキングスペースなどで仕事をするリモートワーカーという新たな職業層が増えてきています。
本市への移住促進の観点から考えた場合、三浦市は単なるベッドタウンとしての役割に加え、リモートワーカーが働き暮らす場所としても適地であると考えます。
自然環境に恵まれ、都市部と適度な距離を保ちつつも必要に応じて都心へのアクセスも確保できるという本市の立地は、リモートワークを前提とした生活スタイルと非常に親和性が高いのではないでしょうか。
こうした観点から、市としてもリモートワーカーにとって魅力的な移住先となり得るという認識を持っているのか、お考えを伺います。
議員おっしゃるとおり本市は自然環境に恵まれ、都心との間に適度な距離があり、なおかつ会社に出社する場合にも都心へのアクセスがよい立地は、リモートワークを中心とした働き方をしている方が働き暮らす場所として適地であると認識しております。
今答弁頂いた認識の上で、リモートワーカーの移住促進という意味でこれまでに具体的な取り組みがあったのか伺います。
令和4年度に民間事業者からの申出により、デジタル田園都市国家構想推進交付金、地方創生テレワークタイプを活用し、民間事業が行うサテライトオフィスの整備の支援につきまして交付金の申請を行いました。
しかしながら申請の結果交付対象とならなかったため、サテライトオフィスの整備の支援には至りませんでした。
サテライトオフィス支援に向けた交付金の獲得に動いたものの、結果として実現には至らなかったということです。
確かに現在はアフターコロナの状況下で、都心回帰の動きも一部見られます。
しかし一方で、リモートワークという新たな働き方が定着しつつあり、これは一過性の流れではなくて今後も一定の需要が続くものと考えられます。
こうした変化に対応しリモートワーカーが働きやすい環境を整備することは、本市の移住・定住促進においても有効な施策の一つとなるのではないでしょうか。
過去の取り組みを踏まえつつ、今後この領域についてどのような考え方で進めていくのか市の見解を伺います。
アフターコロナにおきましても、リモートワーカーが働き暮らす場所として三浦市が適地であるとの認識には変わりありません。
今後同様にサテライトオフィス事業の整備の事業につきまして民間事業者から申出があった場合など、国の交付金の状況なども踏まえた上で再度取り組んでいきたいと考えております。
私も三浦に移住してきてくださった方とお話をする機会がありますが、リモートワーカーとして本市の住環境にとても満足している方が多い印象です。
移住・定住促進のターゲット層として、リモートワーカーという観点をですね、明確に位置づけていただきたいと思います。
さて、三浦における働く場のもう一つの要素としてワーケーションという概念があります。ワーケーションはワークとバケーションを組み合わせた造語であり、先ほど取り上げたリモートワークの普及とともに自治体や企業での導入が進んでいる働き方です。
本市は豊かな自然環境や都心からの適度な距離といった強みを持ち、ワーケーションの受入れ地としても十分な可能性を備えていると考えます。
また、ワーケーションを契機に三浦に継続的に訪れる関係人口を増やし、最終的には移住・定住へとつなげることも期待できるのではないでしょうか。
こうした観点から、まず市としてワーケーションを特色とした宿泊施設やコワーキングスペース、サテライトオフィスなどの受入れ環境や利用実態を把握できているのか認識を伺います。
市内の宿泊施設において、ワーケーションとして利用された実態については把握しておりません。
コワーキングスペースについては三浦海岸駅周辺に2か所あると承知しておりますが、利用状況などについては把握しておりません。
ワーケーションは、仮に短期であったとしても滞在する中で三浦市を知ってもらえる機会にもなり、宿泊需要の喚起すなわち観光政策につながると思いますが、この部分の認識についてお聞かせください。
議員のおっしゃるとおり、ワーケーションを目的として三浦市に来ていただくことは宿泊の需要喚起や飲食その他の需要、消費につながり経済効果が見込まれると考えております。
状況は理解をしました。ワーケーションの一形態である企業研修合宿の場としても、本市は大きなポテンシャルを秘めていると思います。
実際に三浦の民宿を貸し切り宿泊込みで研修を実施した方にもお話を伺いましたが、日常業務では得られない非日常空間でのコミュニケーションが促進され、交通の便のよさに加え新鮮な魚介類や野菜を使った食事も大変好評だったとのことでした。
一方で、Wi-Fi環境やプロジェクターなどの研修設備が十分でない点は課題として挙げられていました。
それでも、研修合宿の場としての認知がもっと高まっていいのではないかとの声もありました。
これはどちらかと言えば移住・定住施策というよりもツーリズムとしてのワーケーションという領域に属しますが、本市の観光政策上の課題である消費単価の低さにも対応し得る可能性があり、検討の価値はあるのではないでしょうか。
もちろん基本的には民間が主導で進めるべき領域ですが、例えば実証実験的な形で行政が取り組むきっかけをつくることなど、施策として現実的な取り組みもあるかと思いますので検討をお願いします。
さて、今はスポット的なワーケーションの話でしたが、コワーキングスペースやサテライトオフィスの活用が日常化し、利用者同士がつながることで地域に根差したコミュニティーが形成されることも期待できます。
こうした視点について、市としてどのように考えているのかお伺いします。
個人でスキルを有し場所に縛られずに働ける方に、三浦市を活動の場所として選んでいただくことは大変有益なことと考えております。
また、コワーキングスペースなどでは、事業者が偶発的に出会うことでそれぞれのスキルが結びつき新たなアイデアが地域で展開するなど、相乗効果があると聞いております。
コワーキングスペースや、サテライトオフィスの利用者のコミュニティー形成が進んでいくことは理想的でありますが、市が積極的に推進することは難しいと考えております。
しかしながら、その集まりの中で業種交流会の開催などの支援や、観光協会や商工会議所に加入するなど地域のネットワークへのコーディネートは可能であると考えております。
さまざまな担い手の連携・協働は、事業の継続、地域の活性化に必要であると認識しており、相談者から事業拡張などに係る相談があった際は適切に紹介、マッチングできるよう努めてまいりたいと考えております。
現実的な方向性について答弁を頂きました。
私自身ですね、普段から市内のコワーキングスペースで仕事をしていますが、そこでは多様なスキルやバックグラウンドを持つ方々が集まり、新たなつながりが生まれる場となっていると実感しています。
これまで確認してきたように、本市に居住する若年層の個人事業主やリモートワーカーの存在は今後の移住・定住促進を進める上で重要な要素であり、結果として地域活性化にも寄与し得る大きな可能性を持っています。
行政として具体的な支援にどこまで手を出せるのかは難しいところですが、こうした層が本市を選び定着できる、定住できる環境を整えていくことは、今後の移住・定住政策の中でも重要なポイントとなってくると考えています。
ぜひ今後の政策立案においても、こうしたターゲット層の視点を意識しながら施策を検討していただきたいと思います。

さて、(3)子育て賃貸住宅の運営状況に移ります。
子育て賃貸住宅の供用が開始されてから約8か月が経過しましたが、若年層の移住・定住政策を考える上で、子育て賃貸住宅に移り住んだ方々の暮らしぶりを把握・分析することは当然ながら重要になってきます。
入居者からさまざまな意見を聞いていると思いますが、まずポジティブな声についてどのようなものがあるのかお聞かせください。
子育て賃貸住宅の入居者に対しましては、2月13日から19日までの期間におきまして、チェルSeaみうらでの暮らしや施設、スタッフに対する満足度、施設の利用状況などをお聞きする入居者アンケートを実施させていただきました。
半数に当たる13世帯からの回答がございました。
チェルSeaみうらでの暮らしの満足度を聞いた設問では、全体の約7割の入居者が満足から不満までの5段階評価のうち、満足、やや満足、普通と回答しており、イベントや地区の行事があって楽しい、外で遊んでいると入居者や地域の人が声をかけてくれるなどといった声が寄せられております。
また、施設の利用状況を聞いた設問では、1階にある図書館、南下浦分館につきまして、よく利用する、時々利用すると回答した入居者は全体の8割を超え、新しくきれいな本が多くうれしい、自習室と閲覧スペースが仕切られているためこどもと一緒でも利用しやすいといった声が寄せられております。
子育て賃貸住宅の入居者に対しましては、2月13日から19日までの期間におきまして、チェルSeaみうらでの暮らしや施設、スタッフに対する満足度、施設の利用状況などをお聞きする入居者アンケートを実施させていただきました。半数に当たる13世帯からの回答がございました。
チェルSeaみうらでの暮らしの満足度を聞いた設問では、全体の約7割の入居者が満足から不満までの5段階評価のうち、満足、やや満足、普通と回答しており、イベントや地区の行事があって楽しい、外で遊んでいると入居者や地域の人が声をかけてくれるなどといった声が寄せられております。
また、施設の利用状況を聞いた設問では、1階にある図書館、南下浦分館につきまして、よく利用する、時々利用すると回答した入居者は全体の8割を超え、新しくきれいな本が多くうれしい、自習室と閲覧スペースが仕切られているためこどもと一緒でも利用しやすいといった声が寄せられております。
今前向きなご意見について確認をしましたが、逆にネガティブなご意見が本市の目安箱にも寄せられていることも事実です。
改めて、そうしたご意見の概要とともにその後の対応状況についてお聞かせください。
子育て賃貸住宅に対する目安箱の投書内容でございますが、まずキッズガーデンの活用を求める意見がございました。
キッズガーデンの活用につきましては、親子で参加できるイベントといたしまして、本年1月にペットボトルボウリング大会を企画し入居者同士の交流を促しております。
今後はさらなるキッズガーデンの充実を図るため、ベンチやテーブル等を入居者参加型のワークショップにて製作するなど、指定管理者と検討を進めているところでございます。
また、子育て賃貸住宅の共用部の掃除を入居者で行うことに対して意見がございました。
入居して間もない入居者の方々に対しまして、ご近所付合いの機会を創出することを主な目的として企画したものでございましたが、掃除に対する入居者の負担が大きい状況から入居者の参加の在り方につきまして抜本的に見直すこととして、指定管理者と協議を進めているところでございます。
直営でないことによる対応の難しさというのもあるかと思いますが、住民の方が抱える不満の解消に向けて、市としても引き続き指定管理者との協議を進めていってほしいと思います。
ちなみに最近子育て賃貸住宅から2世帯が退去することになったと聞き及んでおりますが、この退去の理由を把握していればお聞かせください。
おっしゃるとおり2世帯の退去の申出がございました。いずれも一身上の都合によるものでございます。
退去の真意については、確認がなかなか難しいところなのかなと思います。
居住者の想定として、市内で新しい物件の購入までに一時的に住むというような選択肢を取ることはある意味で自然なことです。
不満による退去でないことを願うばかりですが、いずれにせよ空き室となった部屋がなるべく早く埋まってほしいと思います。
実際に入居された方とお話しする中で、同年代のこどもを持つ入居者同士のコミュニティーができたことがありがたいというお声も頂戴しています。
現在の子育て賃貸住宅の入居可能期間は、小学校卒業までもしくは入居の日から10年間のいずれか短い期間とされています。
入居後ある程度の年数を経てよりいいコミュニティーが形成される中で、最長で10年間という入居期間が短いという声も聞かれます。
例えば入居可能期間をこどもの義務教育が終了するまでの期間、すなわち最長で15年にするという選択肢もあったかと思いますが、この期間の延長という可能性について現状どうお考えかを聞かせてください。
こちらの子育て賃貸住宅につきましては、三浦市への定住の足がかりとなる施設でございます。
より多くの子育て世帯に入居していただきたいという考えから、現行の入居可能期間のとおり今後も運営していきたいと考えております。
より多くの子育て世帯に入居してもらうことを優先するということで理解をいたしました。
さて、本事業が目指すのは子育て世代が生活しやすい住宅を供給することだけではなく、入居者同士、そして入居者と地域住民のコミュニティー形成が促進されることだと理解をしています。
このコミュニティー形成支援も指定管理者の重要な業務となるわけですが、現状の取り組み内容について伺います。
こちらの施設の供用開始から3年目までをふ化期、それ以降を成熟期といたしまして、自立したコミュニティー形成を目標として事業に取り組んでいるところでございます。
ふ化期におきましては、指定管理者が主導して入居者のウエルカムパーティーの開催やイベントの実施などに取り組み、コミュニティーの形成と自立を促進する期間としております。
このことから、昨年10月には入居者同士の顔合わせの機会といたしまして、南下浦コミュニティーセンターの多目的ホールにおきましてウエルカムパーティーを開催し、また先ほど答弁させていただいたとおり、キッズガーデンにおきましてもこども連れで参加しやすいペットボトルボウリング大会を開催させていただきました。
参加者からは、入居者同士で交流ができて楽しかった、イベントの参加を通じて関係が深まっていくので今後も企画してほしいといった声が聞かれております。
今後も指定管理者とともにコミュニティー形成につながるイベントを企画してまいりたいと考えております。
ここの動きについてはですね、以前の一般質問でも早急な取り組みを求めていた部分でありますが、ようやく目に見える形で動き始めたと理解をしました。
引き続き、市としてもモニタリングを含め積極的な関与をお願いしたいと思います。
ちなみに地域住民とのコミュニティー形成という観点に立てば、地元自治会との連携も必要になってくるはずです。このあたりの状況について概要をお聞かせください。
昨年10月のウエルカムパーティーにおきまして、地元区でございます上宮田第2区の役員の方も出席をしていただきました。
自治会活動を紹介する機会を設け、その後、自治会への加入の手続で進んでいったと伺っております。
一方で、今回の入居者アンケートの回答内容によりますと、自治会に加入したものの自治会活動にはまだ参加ができていないという実態があることも分かっております。
おっしゃるとおり、地元との連携はコミュニティー形成の観点からも非常に大切であると考えております。
今後も自治会をはじめ、関係部署や指定管理者と共に、一層連携してコミュニティーの形成に取り組んでまいりたいと考えております。
状況について理解をしました。
市の事業として整備されたこの子育て賃貸住宅の住民が地域に溶け込めているか否かというのは、これから移住を検討してくださる若年層にとっても大きな関心となるはずです。
入居された方から、住環境として本当に満足しているというお声を頂戴することもありまして非常にうれしく思うところですが、本事業のコミュニティー形成の部分については、まだまだこれからといったところだと思います。
今後のより積極的な取り組みに期待をしております。

さて、最後の項目である個別事業の現状と課題についてです。
あとちょっとですので、もう少しお付き合いください。
これまで私が考える若年層の移住・定住のために間接的に重要になる項目を確認してまいりましたが、総括も含めて市が掲げる直接的な移住・定住支援施策について問いかけます。
まず初めに三浦移住学についてです。
これは今は東京、横浜など他の地域で暮らしているけれども、近い将来は三浦に引っ越して新しい生活をしたいと考えている方のための移住講座ということですけれども、これまでに計7回開催されたと聞き及んでおります。
これまでの参加者数の推移と累計人数について伺います。
三浦移住学は令和3年度から実施しております。同年度に実施しました第1期の参加者数は15名でありました。
また令和4年度に実施した第2期と第3期では、それぞれの参加者数は5名と11名であり、令和5年度に実施しました。
第4期と第5期は、それぞれの参加者数は11名と18名でありました。
本年度は第6期と第7期を実施いたしまして、それぞれの参加者数は14名と13名でありました。累計人数は計87名となっております。
87名の参加者のうち、実際に移住された方は何名いるのかお聞かせください。
三浦移住学に参加された方のうち、実際に移住された方は6名でございます。
実は何を隠そうですね、私も議員になる前、三浦にUターンする直前のタイミングで第1回目の三浦移住学に参加をさせていただいた経緯があります。
実際に移住したのは恐らく私も含めて6名ということで、実績としてどうなのかは判断が難しいところです。
しかし個人的な実感として、移住学に参加したメンバー同士はいまだに交流がありまして、結果的に移住はしなかったものの、三浦のファンになってくれた方も少なくありません。
関係人口の増加に一役買っている側面もあるかと思いますので、今後の実施にも期待をしたいところです。
さて、もう一つ直接的な移住支援の施策として、移住冊子の発行があります。現在発行されている移住冊子の作成時期と発行部数について伺います。
現在の移住冊子は令和2年度に作成いたしまして、発行部数は1万部でございます。
こちらの冊子の配架状況がどうなっているのかをお聞かせください。
移住冊子は、主に有楽町にございますNPO法人ふるさと回帰支援センターでの配架をはじめ市内の店舗等への配架、三浦移住学参加者や移住相談に来られた方へ配布をしている状況でございます。
令和7年2月25日現在における残部数は873冊であります。
この配架状況について、配架先からのフィードバックも含めて市としてどのような感触を持っているのかお聞かせください。
主な配架先でございますNPO法人ふるさと回帰支援センターからは、他の自治体の移住冊子と比べ三浦市の移住冊子はクオリティーが高く、多くの方々が手に取られコンスタントになくなっているとの話を頂いております。
移住に関心のある方に対し、訴求力のある冊子であると感触を持っているところでございます。
確かに全体としてデザイン性が高く、都心の忙しさや慌ただしい生活から離れてゆとりのある暮らしを求める人々に対して、三浦での生活の魅力を伝えるという点では、とてもいい内容だと感じています。
一方で、例えば子育て世代が三浦での生活をより具体的にイメージできるような情報がもっと盛り込まれていいのではないかなと思います。
来年度新たに移住冊子を作成する予定と聞いておりますけれども、新版発行に際しどのような点を重視して作成する予定なのか伺います。
現在の移住冊子は、移住に関心ある方に移住先として三浦を選んでいただくためのものであることを踏まえ、若年層をターゲットとし三浦市に住む魅力が伝えられている内容であること、また冊子という形態であることを踏まえ、手に取りたくなるようなインパクトのあるものであることなどをポイントとして作成しております。
来年度作成予定の移住冊子に関しましても基本的にはこの考え方を踏襲する考えでございますが、議員ご指摘の点につきましても作成の際には十分参考にさせていただきたいと考えております。
若年層というある意味漠然としたターゲット設定ではなくて、どのようなライフスタイルや価値観を持つ若年層に響かせたいのか、そのマーケティング戦略を明確にした上で作成にあたっていただきたいと思います。
さて、本年度から創設された結婚新生活支援補助金がありますが、まさに若年層の移住・定住支援として直接的なアプローチとなる施策だと思います。
支給要件なども含めて、改めて制度の概要について伺います。
結婚新生活支援補助金でございますが、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された世帯を対象としまして、結婚を機に市内で新たに住宅を取得した費用や賃借する際に要した費用、引っ越し費用、リフォーム費用に対して、夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、夫婦ともに39歳以下の場合は最大30万円の補助金を支給する制度でございます。
結婚の前後には出費がかさみますから、対象者としてはありがたい制度だと思います。
もう少しで本年度分の申請締切りを迎えるわけですけれども、現在の申込み状況がどうなっているのかお聞かせください。
令和7年2月25日時点における申込み件数は1件でございます。
なかなか厳しい数字ですけれども、この申請者数の少なさについてどんな要因があると分析しているのか伺います。
本事業は国庫補助事業でございますが、対象世帯の要件として、夫婦の年間合計所得額を500万円未満と設定することが要件となっております。
同様の事業を実施している他の自治体や神奈川県との意見交換の中では、この金額が低過ぎることが利用が伸びない要因となっているのではないかと、そういう話が出ております。
本市も同様の認識がございまして、大きな課題であると感じておるところでございます。
おっしゃるとおり共働きが一般的となった現在において、夫婦の合計所得が500万円以下という要件については、特に30代となると対象者が限られてくると思います。
厳しい財政状況の本市にとって、単純な現金給付の事業というのは国の財源を活用するのが現実的ですから、もう少しこの要件を緩和できるよう県や他の自治体とも協働して国へ要望していってほしいところです。
さて、最後に移住ポータルサイトについてです。移住を検討してもらう上で、自治体の移住関係のページは重要なツールとなってくるはずです。
本市の移住ポータルサイトについては過去の質問でも何度か取り上げておりまして、ちょうど1年前の令和6年第1回定例会での一般質問では、神奈川県から派遣された移住・定住促進アドバイザーの報告を踏まえ、更新を図るとの答弁がありました。この部分についての進捗を伺いたいと思います。
神奈川県から派遣されました移住・定住促進アドバイザーからは、令和6年3月にポータルサイトに対する助言や改善策について報告を受けております。
その後募集中のイベント情報をページ情報に掲載することや、三浦市で開業及び開店した移住者を紹介するページのリンクバナーを大きくするなどページを見やすくする更新は行いましたが、アドバイザーからの助言や改善策を踏まえた直接的な更新作業は行うことができておりません。
今後更新作業を進め、本年度中をめどに更新作業を終えたいというふうに考えているところでございます。
これから本格的に着手をしていくとのことです。
結びとなりますが、今回の一般質問では多部門にまたがるテーマを扱いました。
それぞれの分野において既に取り組みが進んでいる部分と、今後解決すべき課題が明確になったと感じています。
限られた予算とマンパワーの中で、職員の皆さんが現場で日々奮闘されていることも改めて実感をしました。
私の政治家としての持論ですけれども、全ての市民が満足する施策を打つことは現実的に困難だとしましても、全ての市民に納得感を持ってもらうこと、そういった施策を考えることは不可能ではないと信じています。
私の知る限り、これまでの一般質問でEBPMが取り上げられたことはなかったと思います。
どのような手法であれ、政策の意思決定プロセスを強化することこそが市民の納得感を高めるための重要な土台であり、これからの三浦市政に必要な要素になってくると考えます。
今回の質問では決して簡単ではないテーマも含まれましたが、真摯にご答弁いただきましたことを感謝申し上げます。

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。