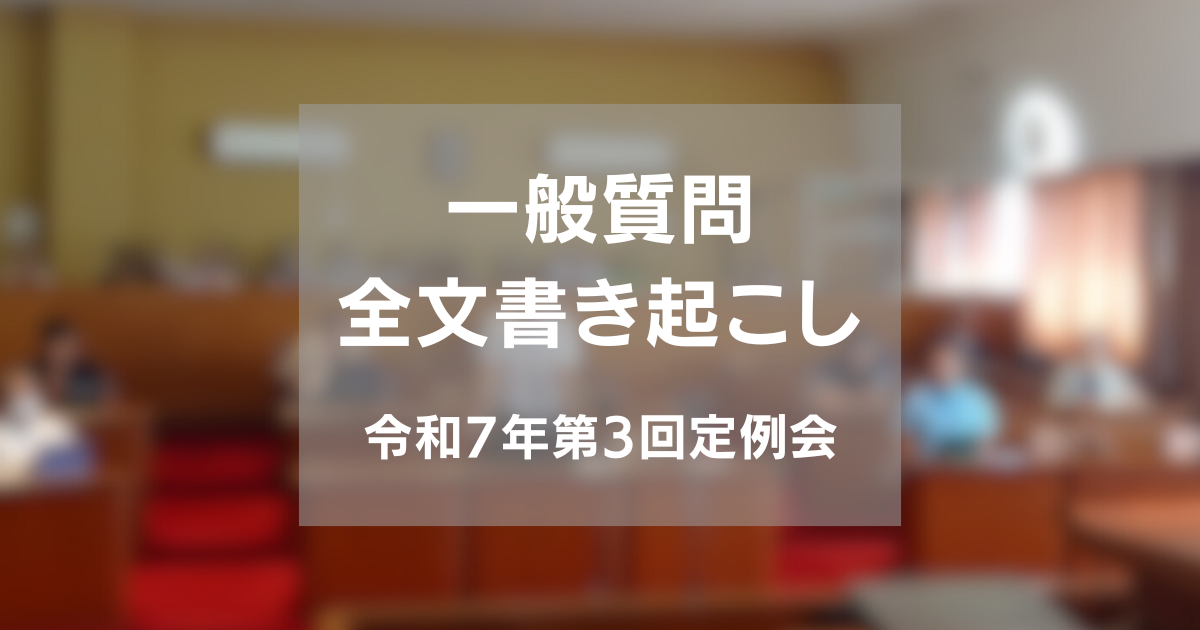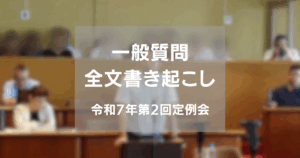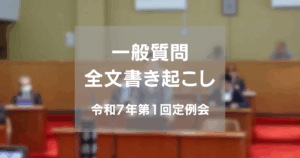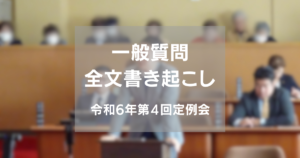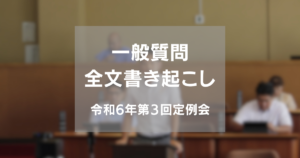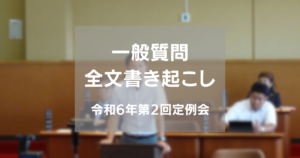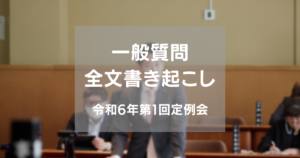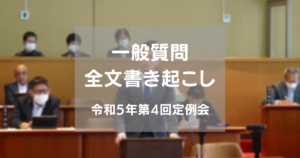令和7年第3回定例会のうち、9月8日に行われた私の一般質問について、自分で書き起こした全文をアップします。
一般質問については、以前の投稿(初めての一般質問を終えて)で概要をご説明しておりますので、よろしければご覧ください。
※展開がわかりやすいように、吹き出し風の文章を適宜挿入します。
※行政からの答弁、その他議員の発言については、囲み文字で記します。
※議場での発言には議長の許可が必要なので、実際には議員、職員ともに発言ごとに挙手→議長からの許可の流れがありますが、ここでは便宜的に省略します。
「一般質問なんて聞いたことがない」
「聞いていてもつまらない」
そんな感想をお持ちの方も少なくないと思います。
私としてもそのお気持ちがよくわかるので、手元に資料がなくても話の流れがつかめるよう、構成や原稿はできる限り工夫しております。
興味のある分野だけでも拾い読みしていただけたらありがたく思います。
そして感じたこと、思ったことなど率直なご意見をSNSやお問い合わせフォームから教えていただけたら幸いです。
※発言の内容は下記の通告書通りになります。
1.カムチャツカ半島沖地震への対応
(1)市の対応と当時の状況把握
(2)市の体制について
(3)課題と今後の取組
2.子育て支援(未就学児)の取組と今後
(1)妊娠~出産前の支援
(2)新生児~幼児期の支援
(3)令和7年度新規の取組
※クリックすると該当部分にジャンプします(画面右下の矢印ボタンで最上部に戻れます)
下記の文章はあくまで私がYoutubeでのアーカイブ配信を個人的に書き起こしたものであり、正式な議事録ではありませんのでご了承ください。
議事録がアップされましたらこちらにそのリンクを追記する予定です。
以下発言

おはようございます。
ただいま議長の許可を頂きましたので、三志会の一員として質問をさせていただきます。
質問は、発言通告書どおり、1番、カムチャツカ半島沖地震への対応、2番、子育て支援(未就学児)の取組と今後の2点となります。
一問一答方式で質問をさせていただきますので、ご答弁のほど、よろしくお願いします。
1.カムチャツカ半島沖地震への対応
まず、1番目の『カムチャツカ半島沖地震への対応』を取り上げます。
本題に入る前に、今回の地震の概要について整理をしておきたいと思います。
先月の7月30日午前8時25分頃にカムチャツカ半島東方沖の深さ35キロで発生した地震は、マグニチュード8.8という大規模なものでした。
この地震に伴い、我が国の太平洋沿岸には津波警報が発令され、本市を含む神奈川県沿岸部でも一時的に避難行動が求められる事態となりました。
結果として市内で大きな被害は確認されなかったものの、市民生活に直結する避難情報の発信や避難所の開設、さらには市民からの問合せ対応など、行政としての危機管理の在り方を改めて問われる出来事であったと考えております。
そこで、今回は、本市の対応を時系列で整理し、どのような課題があったのかを確認した上で、今後の改善に向けて議論を展開してまいります。

初めに(1)市の対応と当時の状況把握に入ります。
同日9時40分に津波警報が発表されてから翌日の津波注意報解除までの市としての対応の概要について、時系列で確認をしていきます。
まずは、津波警報発表から避難指示までの対応についてお聞かせください。
9時40分の津波警報の発表に伴いまして、同時刻に災害情報センターの設置及び避難指示を発表いたしました。
災害情報センター、これは後ほど確認しますけれども、この設置を行って、避難指示を即刻出したとのことです。
それでは、この避難指示を行ってから後の避難所開設までの対応について伺います。
防災危機対策室では引き続き情報収集を行い、公共施設を所管する各担当部署では避難者の受入れや施設内にいる市民の避難誘導を行いました。
沿岸の公共施設では業務を中止したほか、避難者がいる公共施設には保健師を派遣し、避難者の健康状態の確認を行いました。
また、14時30分に市長、各部長による対策会議を開催いたしまして、16時に避難所を開設することといたしました。
避難所開設の時間の是非については後ほど議論しますが、事実として14時30分に対策会議が開催され、16時に避難所開設の運びとなったとのことです。
避難所開設後から津波注意報解除までの対応についてはいかがでしょうか、伺います。
避難所開設後は、避難所を市の職員で対応し、引き続き情報収集を行いました。
また、三崎口駅及び三浦海岸駅の帰宅困難者に対しましては、避難所までの案内を作成し、配布いたしました。
その後、翌日の10時45分の津波注意報の解除に伴いまして、同時刻に避難指示を解除し、災害情報センターを閉鎖いたしました。
時系列で市の対応を確認させていただきました。
少しそれぞれの内容について深掘りしてまいりますが、まずは避難指示についてです。
この避難指示については、発表の基準や情報の発信方法、避難行動について、事前に定められているのか伺います。
避難指示は、三浦市地域防災計画の基準により、津波注意報以上で発表することとしております。
情報の発信方法につきましては、三浦市地域防災計画で防災行政無線を使用し発信することとしております。
避難行動といたしましては、近くの高台へ移動し、避難所へ向かうときは標高の低い位置を通らない経路で避難することを日頃から周知をさせていただいております。
今答弁にあった三浦市地域防災計画、これは災害対策基本法第42条で策定が義務づけられた計画ですが、これに伴った対応が原理原則になるのだと思います。
情報の発信方法としては、防災行政無線以外にもさまざまなツールが使用されたと思います。ほかにどのようなものがあったのかお聞かせください。
広報で使用したツールといたしましては、防災行政無線、防災メール、市の公式LINE、市のホームページをして使用しております。
三浦市地域防災計画の137ページには、津波警報並びに津波情報及び津波予報の受理伝達として、市及び防災関係機関はあらゆる手段の活用を図る旨の記載があります。今列挙されたのが、ここに記載されたあらゆる手段に該当するのだと思います。
ちなみに、現在、防災危機対策室のX、旧ツイッターですけれども、こちらで情報を見ることができない状況になっています。この状態になった時期と理由についてお聞かせください。
これまで主に防災行政無線にて放送した防災情報等を防災危機対策室のXアカウントにて発信をしておりましたが、2023年7月24日に旧ツイッターからXへ名称変更されたことに伴いまして、防災行政無線との連携ができない状況となりました。
再度連携を行うためにはシステム改修等が必要となるため、現在、Xで情報を見ることができない状況となっております。
防災情報等は、防災行政無線、防災情報メール、市の公式LINE、市のホームページで発信をしておりますが、あらゆるツールを使って情報を届けることにつきまして検討を行ってまいりたいと考えております。
SNSにもさまざまな種類があり、使用する年齢層や属性が異なってきます。
今回、システム改修が行われなかったためXは使えなかったわけですが、それ自体の是非を問うというよりは、一人でも多くの市民に効果的に情報を届けるために、どのSNSの活用が必要になってくるのか、改めてゼロベースで考えていただきたいと思います。
さて、スマートフォンなどが使えない市民の方にとっては、防災行政無線の情報が大切なよりどころとなってきます。
今回、沿岸部だけではなく市内全域に、しかもかなり断続的に放送を行ったわけですけれども、その理由について伺います。
放送を市内全域に行った理由といたしましては、高台にいる人たちにも海に近づかないよう周知する必要があったと判断したためでございます。
継続的に放送した理由といたしましては、聞き逃した人または聞き取れなかった人がいないようにする目的で実施をさせていただきました。
防災行政無線のやり方についてはさまざまな感じられ方がありますから、一概に正解が何かを見いだすのは難しいんですが、いずれにせよ、明確な意思を持って今回の運用に至ったということです。
さて、行政側の対応や状況について市民からの電話による問合せは相当数あったのではないかと思われますが、そのあたりの状況はどのようなものであったのか伺います。
防災危機対策室の電話が問合せ等で全て塞がってしまう状況が長く続いておりました。
本来、電話対応よりも行政内部での情報収集や対応検討に努めるべき防災危機対策室の電話がパンク状態になったことは、あまり望ましい状態ではなかったのかなと感じます。
何か適切な対応は取られたのでしょうか。
このあたりの根本的な原因についても後ほど議論したいと思います。
さて、今回、市側の基本的な初動対応としては、自主避難を呼びかけるというものでした。
自主避難先の状況について確認をしていきますが、まずは、公共施設はどのような状態だったのか伺います。
市内の小中学校や第2分館、市民センター等の公共施設に多くの方が避難されている状況でございました。
スーパーや公共交通機関はどのような状態だったのでしょうか。
大型スーパーのベイシアにも多くの方が自主避難をし、三浦海岸駅周辺には帰宅困難者が発生し、上宮田小学校への避難誘導が行われました。
また、三崎口駅周辺の帰宅困難者に対しましては、京急バスがバスを待機場所として提供をしていただきました。
ピーク時にはそれぞれの場所でどのくらいの人々が自主避難をしたのかお伺いします。
公共施設のピーク時は避難者数1,213名でありました。
また、ベイシアの駐車場は満杯の状況となっておりました。
各施設だけではなく、道路も大変な状態であったと耳にしています。
避難による道路状況はどのようなものであったのか伺います。
道路の渋滞情報でございますが、城ヶ島大橋の渋滞と油壺入り口を先頭とした上り線の渋滞が発生しております。
また、コンビニエンスストア・ミニストップ三浦池代店の駐車場が満杯になったことにより、車両が道路にはみ出すなどの状況となっておりました。
一部メディアでも道路の混雑状況が取り上げられていましたけれども、車で避難される方が短時間で集中してしまうこと、これも津波発生時の大きな懸念点だと思います。
逆に、炎天下の中、徒歩で避難した方も少なくなかったはずです。
避難に伴う熱中症患者の報告事例はあったのかお聞かせください。
三浦消防署に避難に伴う熱中症患者の救急搬送について確認をしたところ、そのような事案は発生していないとのことでございました。
また、救急搬送以外の熱中症に関する情報も、現時点では報告の事例はございません。
熱中症患者の報告事例はなかったとのことです。
ただし、震災の状況によっては熱中症のリスクがさらに高まっていた可能性もあります。
あくまで不幸中の幸いであったことを忘れず、熱中症への対策が万全だったのかについても、今後しっかりと検証を行ってほしいと思います。
少し話は変わりますが、津波警報発出時における保育園・幼稚園の避難等の対応状況についてお伺いします。
各施設はそれぞれの判断で避難対応等の行動を行っております。
各施設からの報告によりますと、津波被害が想定される地域に位置する施設につきましては、迅速に避難を実施しております。
一方で、津波被害の可能性がない地域に位置する施設につきましては、特に避難等を行うことはせず、通常どおりの運営を継続したと報告を受けております。
こどもを預けている親御さんにとっても気が気ではなかったと思います。
今の答弁から、特段大きな混乱はなかったと認識をしました。
それぞれの園が実施した具体的な避難行動は、市が事前に想定していた内容と合致していたのか、その認識をお聞かせください。
現在、当日の対応状況につきまして、アンケートを用いた調査を進めているところでございます。
避難行動につきましては、各施設が持つマニュアル等に基づく対応になりますが、その内容については現時点で市は把握していないため、必要に応じて各施設からマニュアル等の提供を求め、共有を図ってまいりたいと考えております。
現状、当時の対応状況については検証中であるとのことです。各園のマニュアルを市は把握していないとのことですが、まずは、各施設にマニュアルの提供を求め、市としても避難行動のガイドラインを策定するなど、園児たちや先生方がより安全に行動できるような備えを強化していただきたいと思います。
話を戻しますが、自主避難先での水分や食料の配布について、現場ではさまざまな混乱の声が聞かれました。
この部分について市はどのような考え方で向き合ったのかをお尋ねします。
備蓄食料等は、大規模災害が発生し、長期の避難生活を余儀なくされる方へ配布する目的で備蓄をさせていただいております。
今回は地震等による被害が発生していない状況でございまして、ライフラインも寸断されてない状況でありましたが、水道水が苦手という市民の方もおられると思い、自分でお飲みになる飲料水等につきましては、自助のお願いをさせていただきました。
確かに今回水道が止まっていたわけではありませんし、津波の到達まである程度の時間がかかることは伝えられていました。
しかし、防災情報メールでも今すぐ高台に避難することが呼びかけられる中、飲料や食料を持参することを考えられなかった方もいらしたと思います。
ここについては、普段からの自助の意識をもっと高めなければならないということもあるのかもしれません。
しかし、現場が混乱したのは、いつ避難所が開設されるのかも分からない、自宅に帰っても大丈夫だとも言えない状態の中で、行政からの情報がほとんど入らないまま、避難者の中で漠然とした不安が募っていたからではないでしょうか。
情報の出し方という意味では間違いなく改善すべきポイントがあったように思います。
今は状況確認を優先してここについては追って伺います。
いずれにせよ、自主避難先では今後の動きについて不安が渦巻く中、いろいろな葛藤の中でやむなく飲料などの配布が行われた現場もあったと聞いています。こうした事実を市側は把握しているのか伺います。
現場での判断で食料や飲料水が配布された報告は受けております。
そうしたやむなく放出した備蓄品の補塡については考えられているのか伺います。
放出をいたしました備蓄につきましては、補塡することを検討しております。
ここまでで市の対応についての諸々の事実確認を行ってきました。

ここからが今回の本議論の本題であり、私が対応についての是非を問いたいところです。
(2)市の体制について、に入ります。
先ほど答弁の中で、今回の市側の体制としては、災害情報センターを設置して対応に当たったとのことでした。
この災害情報センターはどのような組織で、どのような対応が行われるものなのかをお聞かせください。
気象警報が発表された場合、防災危機対策室の執務室に災害情報センターを設置し、防災危機対策室の職員が災害に関する情報の収集を開始いたします。
設置をした旨を庁内、消防、警察等に連絡いたしまして、災害に関する情報は災害情報センターに報告するよう周知をすることになっております。
あくまでこの組織はですね、防災危機対策室の内部に設置されるものであり、主な機能は情報収集の一元化であると思います。今回の対応についてきちんと検証されるべきなのが、三浦市地域防災計画にも記載され、職員の配備体制や動員指令についての権能も明確となっている災害対策本部、これを設置しなかったことの是非であると私は思っています。
なぜ今回災害情報センターの設置にとどまり、災害対策本部の設置が行われなかったのか、まず、担当課に答弁を求めます。
災害対策本部の設置基準は大津波警報が発表された場合等となっております。
今回は津波警報であったことから、災害対策本部の設置は行いませんでした。
そうですよね。
確かに三浦市地域防災計画には災害対策本部の設置基準の一つとして、相模湾・三浦半島予報区に大津波警報が発表されたときという記載があります。
防災危機対策室の判断基準としては、当然設置ができなかったということになります。
しかし、設置基準の中にはですね、「その他市長が災害対策本部の設置を必要と認めるとき」という記載もあるんです。
つまり、市長権限で災害対策本部の設置を決断することができたわけです。
災害への備えを怠らないまちをつくることを標榜している出口市長ですから、当然この権能については理解をされているはずです。
つまり、今回、積極的な意思を持って災害対策本部の設置を行わなかったということになるわけですけれども、市長、その意図をお聞かせください。
今回、津波警報による津波は最大3メートルと予測されており、本来であれば沿岸地域にいられる方々を対象として避難指示をいたしますが、高台にいる方々にも標高の低い場所へ行かないよう、市内全域に避難指示を発表したものでございます。
また、津波警報は、遠隔地であるカムチャツカ半島沖地震によるものであり、地震による被害はなく、津波が到達するまでの時間も1時間程度あったことから、消防署や消防団も災害を待ち構える体制が整っておりました。
このような状況の中で、市長権限による災害対策本部の設置についても検討いたしましたが、市民が過剰に不安を感じる可能性もあり、実態に即した冷静な対応を取るため、設置を見送りました。
結果的にですね、津波による大きな被害がなかったからよかったものの、もし津波警報発令から1時間後に実際に津波が来ていたらどうなっていたでしょうか。
また、市民が過剰に不安を感じる可能性があったから設置をしなかったという理由も、結果として大きな被害がなかった事後だから言える論拠であり、後づけのような印象を受けます。
いずれにせよ、市長の答弁から判断するに、決断ができなかったというわけではなく、明確な意思を持って設置を見送ったとのことです。
一度、防災危機対策室にお聞きします。
一般論としてで構いません。
災害が起こった際、今回のように災害情報センターが設置された場合と災害対策本部が設置された場合とで、できることや権限、役所全体の動きとしてどのような違いが出てくるのかお聞かせください。
災害情報センターは、防災危機対策室の職員が情報収集を行い、重要な情報につきましては市長へ報告を行います。
その際に市長から指示があれば、防災危機対策室から周知を行います。
災害対策本部が設置された場合には、市長と各部長等が災害対策本部に集合するため、市長指示が速やかに伝えられることになります。
そうですよね。先ほど私の質問の中でも少し触れましたが、あくまで災害情報センターは情報収集のための場なんです。
一方で、災害対策本部は、意思決定者の権能を改めて明確にし、情報収集に加えて、市長名で職員の動員指令など積極的な指示が出せる体制になることが大きな違いになると思います。
私は今回その動きが明らかに不足していたと感じています。
そもそも今回津波警報が発令された時点で、窓口業務の縮小やそれに応じた災害支援のための職員配備の動きが取られていたのかお聞かせください。
魚市場、初声市民センター、南下浦コミュニティセンターでは、業務を一旦停止し、来庁者等の避難誘導を行ったことを確認しております。
また、公共施設の各所管課では、災害情報センターへの報告をしながら、施設の職員によって避難者の受入れ等を行っております。
しかしながら、窓口業務の縮小等、全庁的な業務配備の変更は行っておりません。全庁的な業務配備につきましては、今後検討していきたいと考えております。
確かに一部職員が避難者の誘導を行っていたことは私も把握しています。
しかし、窓口業務の縮小などを含めた全庁的な業務配備変更の指示は出せていなかったということです。
もしもっと早い段階で通常業務を縮小して、その分の余剰職員を使って例えば電話対応のチームをつくっていれば、先ほど確認したように電話対応で疲弊していた災害危機対策室の本来の業務はもっとスムーズに行えていたのではないでしょうか。
また、人数が多く集まっていた自主避難先に職員を派遣して、情報収集や直接的な指示を行うこともできたはずです。
災害情報センターの機能だけでは、こうした人員配備の指示は出せなかったと推察されます。
庁内の組織として、市長からのもっと早いタイミングでのトップダウンの指示がどう考えても必要だったと私は思います。
ここで率直な疑問なのですが、一連の対応について、出口市長はどこにいて、どのような働きをしていたのか、具体的にどんな指示を出したのかを含めてお聞かせください。
津波警報の発表に伴い、防災危機対策室へ防災行政無線による継続的な避難指示の放送を行うよう指示し、その後すぐに、理事、総務部長、政策部長、市民部長、まちづくり担当部長、政策課長、人事課長、税務課長、秘書担当課長を市長応接室に招集しました。
その後、防災危機対策室長も合流し、情報収集等を行っておりました。
また、津波警報が長引く可能性がある中で、避難所開設等を判断するため、午後に各部長を招集、協議し、対策会議を開催し、その中で避難所の開設を指示いたしました。
避難所開設などを判断するために、午後に各部長を招集して対策会議を行ったとのことです。
冒頭でも少し触れましたが、この対策会議、何時何分に招集されたのか、改めてお聞かせください。
対策会議において各部長を招集したのは14時30分です。
一旦整理しますけれども、9時40分に津波警報が出てから、同時刻に災害情報センターの設置及び避難指示を出したと。
それから防災行政無線による継続的な避難指示の放送を行うよう指示した後は、この14時30分の対策会議の招集が行われるまで特段の市長指示はなかったということになります。
津波警報の発令からこの対策会議の開催まで約5時間を要しているんです。
その間、特段の人員配備の変更や指示もなく、ずっと市長応接室で待機をしていたということです。
当時私が一番驚いたのはですね、その待機時間中、市長が真っ先に個人のインスタグラムアカウントで避難を呼びかけたという事実です。
三浦市長のインスタグラム公式アカウント「miura_city_mayor」でも同様の避難が呼びかけられていましたが、市長、個人アカウントと市長公式アカウントそれぞれについて、避難呼びかけを行った正確な発信時刻についてお聞かせください。
9時51分に私個人のアカウントで先に発信を行っています。また、10時56分に公式アカウントで発信を行っています。
まさかの答弁に驚いています。
9時51分という役所内が初動対応で大変な混乱状態にある中、市長という本市の災害対応における最高意思決定者がですよ、津波警報が発令されて僅か約10分後に、自身の職務よりも優先して個人アカウントで避難を呼びかけていたことになります。
しかも肝心な職務として運用している市長の公式アカウントで避難が呼びかけられたのは、それより1時間以上も後の話だということです。
こんなことがあっていいんでしょうか。
ちょっとその真意を聞く前に事実確認をさせてください。さきの選挙期間中、出口市長は、インスタグラムの個人アカウントの投稿に対して正当な論拠で抗議のコメントをした市民のアカウントを複数ブロックしていたと耳にしています。
まず、このブロックをしたという行為が事実なのかお聞かせください。
正確な数は把握していませんが、10はいかないと思いますけど、5以内ぐらいのアカウントに対してブロックしています。
そのブロックというのは、今回の避難呼びかけを投稿した当時には当然解除されていたという認識でよろしいですか。
解除はしていません。
聞こえなかったので、もう一度お願いします。
解除はしていません。
これは大きな問題だと思います。
自分にとって気に入らない市民を排除したアカウントを使って、しかも、公務真っただ中のタイミングで優先的に避難の呼びかけを行った時点で市長としての資質を疑わざるを得ません。
どのような意識のもとこの一連の行動を取ったのか、具体的にお答えください。
津波警報が発令しておりますので、まず第一にやるべきことは市民の皆さんに高台に避難していただくことです。その中で、私の個人アカウントで避難を呼びかける、これは津波警報発令の中では私は特段誤った行為ではないというふうに考えています。市民の皆さんの命を最優先にした判断の結果であると申し上げます。
問題の認識がないというところです。
これ、複数問題のポイントがあると思っていて、まず、その先ほどのブロック、市民の方をブロックした状態で発信をしたということもそうなんですけれども、やはり一番は、公務中に個人アカウントの発信をするというところ、ここはまず適切なのかとかもそうなんですけれども、今の答弁の中で、結局、市長の公式アカウント、今いろいろ市長は情報発信のほうで頑張られていますけれども、ここの発信が個人アカウントよりも1時間後になったこの理由にはなってないんですけど、これについてはどうお考えですか。
公式アカウントについても発信するように指示をしています。しかしながら、私自身がやるものと庁内で担当者がやるものと時差が起こるということは、やむを得ないことだというふうに考えています。
これこそトップダウンで即刻指示するべきことだったんじゃないんですか。
そこが問題意識はないというところもちょっと…そういう認識なんですね。
改めて聞きますけども、そのアカウントの情報発信にずれがあったことを含めて、一連の行動について間違っていた、不適切だったという認識はないという認識ですか。
繰り返しになりますが、津波警報、最大3メートルの津波が来る可能性があるという中で、いち早くあらゆる手段を使って避難を呼びかけるというのは、私、市長という立場でやるべきことだというふうに考えていますので、特段誤ったという認識はありません。
(「議長、議事進行」の声)
ただいま市長の答弁が、公務中に自分のアカウントを使用して避難誘導を図ったという部分の発言がありました。
そのことについて特段問題はなかったと言っておりますけれども、職務に就いている間、自分の携帯を利用して自分の正式なアカウントを使わないで発信していること自体、少し問題ではないかと思いますので、時間を取って精査をしていただきたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。
途中でございますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
再開時刻は後ほどお知らせいたします。
暫時休憩
再開いたします。
休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。
休憩前の質問に対する市側の答弁を求めます。
市長。
答弁にお時間を頂き申し訳ございませんでした。
7番議員よりご指摘のあった、私の個人のSNSアカウントから7月30日当日の9時51分に発信した津波避難の情報と、同日10時56分に市の公式アカウントから発信した津波避難の情報の取扱いについてでございますが、まず、公式アカウントからの発信が個人アカウントに遅れる形で発信され1時間差が生じてしまったことについては、結果として適切でなかったと考えます。
当時の私の考えとしては、一定のフォロワーの方々がいらっしゃる私個人のアカウントについて、できる限り多くの方々にいち早く少しでも情報をお届けするため活用を図る趣旨で発信を行ったものでございます。
これに対して、公式アカウントでの発信の遅れについては、災害対応時の私からの指示の仕方を含めた市としての組織運営の在り方について、私自身が同時並行的に把握しつつ対応していたことによるものでございます。
このため、公式アカウントを用いた情報発信の時期や方法について遅れての庁内での相談、指示となりましたが、今考えてみますと、議員ご指摘のような個人アカウントにおけるブロック等に伴う制限の有無や公式アカウントによる発信の持つ重みを意識し、個人アカウントでの発信と併せて早期に相談指示を行うべきだったと考えます。
この点については反省すべきものであると考えております。
ご指摘のように、個人アカウントにおいては、いわゆるブロックさせていただいているアカウントもあります。
今回の公式アカウントによる発信の遅れは、それらのアカウントに関わる方々について、私個人のアカウント上の話ではございますが、事緊急時の情報発信の観点から、結果として市民及びほかの方々との扱いの差を生じさせてしまったものでございます。
この点につきましては、それらの方々に対し、この場を借りておわびしたいと考えます。
市長として災害対応時の危機感の薄さ、そして、市民への対応に差が出てしまうことは大きな問題だと認識しておりましたので、そこについては撤回と謝罪を頂けて少し安堵をしました。
時間が空いてしまいましたので、急ぎ足で先ほどの災害対策本部の設置について話を戻します。
参考までに、近隣の4市1町は災害対策本部もしくはそれに準じた組織を設置していたのかお聞かせください。
横須賀市と鎌倉市は災害対策本部を設置し、逗子市と葉山町は災害警戒本部を設置しております
近隣自治体も軒並み、災害対策本部もしくはそれに準じた災害警戒本部を設置していたということです。
市長、これまでの議論を含めて改めて伺いますが、災害対策本部を設置しなかったという当時の判断は今でも正しかったという認識ですか。お聞かせください。
災害対策本部を設置しなかったことについては、実態に即した冷静な判断であったと考えております。
災害対対策本部の設置については、災害の規模等を考慮し、今後も冷静に判断していきたいと考えております。
分かりました。
先ほど、逗子市と葉山町では災害対策本部に準じた災害警戒本部を設置したという答弁がありました。
本市においては、市長指示がなく災害対策本部が設置できなかった場合、災害情報センターのような権能が限定的な組織ではなく、全庁をまたぐ対策組織を構築するすべはないのでしょうか、お尋ねします。
災害対策本部のほかに全庁をまたぐ対策組織といたしましては、風水害等の際に副市長権限で発令をできます災害警戒本部という体制がございます。
まさに副市長不在のリスクがですね、こういう形でも出てきてしまっているということです。
参考までにお聞きしますが、実際に本市に災害警戒本部はどのようなタイミングで設置されるのか、実績を伺います。
これまで台風接近等により市内で広域的な被害が発生すると予測される場合には、数日前に災害警戒本部を設置した実例がございます。
副市長不在により、本来であれば比較的機動力の高い状態で設置ができる災害警戒本部を設置ができない状態であった。
そういったことも、今回、出口市長が災害対策本部を設置すべきだった根拠の一つであったと私は思っています。
この前提で話を進めますが、多くの市民の方から疑問の声が上がっていた避難所の開設時間についてです。
他市と比較して、本市の避難所設置は不自然なほどに設置時間が遅れました。
私の調べでは、それぞれの自治体における避難所の設置時間は、葉山町が9時40分、逗子市が10時10分、横須賀市が11時40分、鎌倉市が12時40分であったと認識しております。
これらの近隣自治体と比較して、すぐに避難所設置に踏み切れなかった理由について伺います。
津波避難の基本は、三浦市防災ハザードマップに記載のとおり、避難所へ避難することではなく、近くの高台へ避難することであります。
また、避難所まで行く際に標高の低い経路を通ることにより津波被害を受けるおそれもあることから、早期の避難所の設置を見送りました。
市長はそれを判断する上で迷いというものはなかったんですか、伺います。
津波から命を守ることを第一に避難所まで行く際の津波被害防止を考えた末の判断であり、迷いはありませんでした。
確かに避難所を早期に設置することで、本来最初に避難すべき近隣の高台ではなく、経路によっては危険も伴う避難所が一次避難の目的地になってしまうというリスクというのがあったと思います。
その意味で明確な意思を持って早期の避難所の設置を見送ったという判断自体には、一定の理解をしているつもりです。
しかし、その根拠は開設が16時まで遅れたことの説明にはなっていません。
避難所が16時に開設なった根拠についてお答えいただけますか。
津波警報の発表が長期にわたることが想定されたため、屋外の避難場所にいる方々を屋内の避難所へ収容する必要があると考え、昼間の明るいうちに避難所を開設する必要があると判断したということでございます。
市長、今の答弁はですね、避難所の開設を16時以降にしなかった理由であって、16時より早い時間に設置をしなかった理由にはなっていないんですよ。
追ってこの部分の核心は迫りますので、もう次に行きます。
結果的に主な自主避難先となった学校には多くの避難者が駆けつけたと聞いています。災害対策本部が設置されなかったので、各校に対しては教育委員会が何らかのアプローチを行ったものと思います。具体的にどのような指示を出したのかお聞かせください。
避難所の設置の前に、市民、観光客、帰宅困難者等が避難してくる可能性がありました。
その場合には、熱中症予防の観点から、冷房設備のある教室等を開放するなどして受け入れるよう指示をいたしました。
また、避難所開設後はですね、施設管理者であります学校長に対し、午後8時まで残り、市の職員と共に避難所の運営に協力するよう依頼をいたしました。
出勤していた教職員に対しての協力依頼は行っておりませんでしたが、勤務時間内はもとより、時間外も自主的に学校に残り、学校長と共に避難所運営に協力する教職員もいたとの報告を受けてございます。
当時、学校は夏季休業中であったわけですが、出勤されていた先生方が本当にご尽力してくださったというふうに伺っています。
学校には備蓄飲料・食料がありますから、それを放出するという選択肢もあったはずです。
この部分について、市としてはどのような方針を取ったのか伺います。
備蓄食料等は、大規模災害の発生時に放出することを考えているため、今回は原則として放出しない方針としました。
ただし、この点については、熱中症予防などの観点から、今後、より柔軟に対応すべきと考えております。
このような杓子定規な方針を立てることは容易ではありますけれども、その柔軟な対応を、職員を派遣せずに各自主避難先へ委ねてしまったことが問題の一つであったと考えています。
現場で対応に当たっていた方々は、明確な権限を与えられていない中で、行政からの間接的な指示と目の前の避難者からの要望との板挟みに遭い、本当に大変な思いをされたのではないでしょうか。
そこで、備蓄食料放出の方針について、避難所である学校にはどのような指示が出されたのかを伺います。
備蓄食料等を原則として放出しないこと及びその根拠等を学校に伝えました。
あくまでも原則でございまして、各避難所の状況に応じて判断し、場合によっては備蓄食料等を提供してもよいことも、防災危機対策室に確認した上で併せて伝えております。
結局のところ、自主避難先の現場の判断に委ねたということです。
避難所の開設時間に話を戻しますが、16時という開設時間の設定の根拠が教職員の終業時間だったのではないか、という指摘もあります。
避難所設置の本来の目的からすれば、教職員の退勤の時刻に合わせて設置することは根拠としておかしいわけですが、どのような認識でしょうか。
14時30分に対策会議を開催し、避難所を担当する職員を振り分け、避難所までの移動に使用する車両の確保及び移動時間を踏まえ、体制を整えるまでの時間を考慮し、決定したものでございます。
そうですよね。
これまでにも確認してきたとおり、14時30分に初めて全幹部職員を集めた対策会議を開催したわけですから、人員配置等の指示も含め、避難所設置のための準備ができるのはその後、結果的に16時ぐらいになってしまうというのは当然なことなんです。
結局のところ、災害対策本部も災害警戒本部も設置されていない状態で、初の対策会議の開催が14時30分、この時間になってしまったことが、避難所設置がこんなにも遅れてしまったそもそもの理由だとしか考えられないんです。
だから、私は、災害対策本部を設置して幹部職員をもっと早いタイミングで招集できていれば、避難所開設の時間はもっと早められたはずだと繰り返し言っています。
質問を変えますけれども、この対策会議の招集が14時30分まで遅れた理由は何なんでしょうか、お聞かせください。
防災危機対策室は、電話対応にも追われながら、本当によく情報を集めて市長に伝え続けていたと思います。
不足していたのは市長のトップダウンの指示だったんです。
こと災害対応においては、市長はその情報が全部出そろってから判断ではなくて、状況によっては、限られた情報の中でもそのタイミングでの最善を見いだして、責任を持って指示を出すことが必要になってきます。
これが市長に求められるリーダーシップだと思います。
この部分が発揮できていれば、仮に災害対策本部を設置していなかったとしても、今回の対策会議はもっと早く開催できたんですね。
そして、それができていれば、避難所設置はもっと早いタイミングで開設できたはずなんです。
改めてこの指摘についてどうお考えですか。
先ほどの答弁のとおり、災害時の対応については、私自身がまだ経験も浅く、職員と十分に協議、相談を行った上で、より慎重に判断を行うことが適切であるとの考えのもとで今回の津波対応に当たってきました。
判断の迅速さについては、私自身の経験の不足がほかの自治体との対応の差につながっている可能性は否定できないと思います。
今回の教訓を生かして、より迅速な判断ができるよう、今後努めていきたいというふうに考えております。
リーダーシップを発揮するために大切になるのは、日頃からの職員、市長からすると部長級の理事者になりますけれども、そうした部下とのコミュニケーションや信頼関係の構築だと思います。
先ほどのインスタグラムの一件も、職員とのコミュニケーション不足という側面もあったはずです。
これらは、リーダーシップを持って頑張りますという意気込みだけで何とかなる話ではありませんので、ぜひとも日頃から職員との信頼関係を築いてほしいと思います。
次の質問に行きます。
災害時には毎度のことでありますが、今回の津波対応においても、各消防団が懸命に動いてくださったということを耳にしています。
津波警報発表後、各消防団はどのような対応を取ったのか、把握している内容をお聞かせください。
津波警報発表後、津波災害時における消防団安全管理マニュアルなどに基づきまして、消防団本団は団本部室に参集、沿岸地域に立地をしている分団は消防団車両と共に高台へ避難し、高台に立地をしている分団は詰所参集の対応を図りました。
警報が発表されてから注意報に切り替わるまでに時間を要しましたが、その間、消防団員の方々はどのような活動に従事してくださったのでしょうか。
一部の本団員は各高台の避難者の情報の収集、分団は地域住民への避難広報及び一部避難場所での支援活動など、現場の状況に応じた活動を実施いたしました。
本当に迅速に、かつ的確に動いてくださったと伺っています。
今回の津波警報発対応において、現場で動かれていた消防団員の方もいろいろと思うところがあったかと思います。
そうやって浮き彫りになった課題を把握する上でも、市としてどのような取組をしたのかお聞かせください。
8月8日、本団及び各分団宛てに津波警戒に関するアンケート調査を実施いたしました。
アンケートでは、マニュアルの周知状況や今後に向けた課題などの設問率直な意見を確認することができました。
今月末に開催をする消防団会議においてフィードバックを行いまして、課題の改善に向け検討を実施する予定でございます。
そうした機会がしっかりと設けられているとのことで、安心をしました。課題の把握と解消に向けて、有意義な消防団会議になることを願います。
改めて、今回の消防団の方々の対応について市長の所感を伺います。
高温の環境で長時間にわたり消防団員は団本部の指示に対応しつつ、地域住民からの要望にも柔軟に対応されていたと伺っております。
改めて消防団員の尽力に感謝申し上げます。
防団は地域住民とのつながりも強く、特に大規模災害時には地域の安心・安全を支えるかけがえのない存在でございます。
今後も、地域住民の安全・安心のために、日々の研修や訓練に励まれることを心から期待しているところでございます。
私からも改めて心から感謝の意を表したいと思います。
さて、次に、福祉分野における災害対応について話を移します。
まず、避難行動要支援者等に対して、自治会の役員や民生委員の方々が各所でさまざまな対応してくださったと伺っています。
当時の対応について把握していることがあれば伺います。
後日、民生委員の方たちに当日の状況を確認したところ、どのように対応してよいかの問合せがあった、独り暮らしの高齢者宅を軽自動車で回った、高台に住む高齢者の方などには避難所に避難せずに自宅にいるよう電話連絡を入れた、区長と相談し区民会館を開き避難させた、避難所に行き対応した等の話を伺っております。
改めて、日頃より民生委員の方々には、地域の見守り活動をはじめ、大変なご尽力をいただいていることについて感謝を申し上げます。
本当に区の役員の皆様や民生委員の方々のご尽力に対しては、日頃から感謝の気持ちを忘れたくないものです。
ちなみに、今回、要配慮者の二次避難のためにも重要となってくる福祉避難所は開設されたのか確認させてください。
福祉避難所につきましては、今回開設はしておりません。
今回の対応という側面とは別にですね、福祉避難所は災害時に要援護者の受入れという意味で確かなニーズがあるにもかかわらず、全国的に不足が叫ばれています。
さまざまな困難がありますが、本市においても無視できない政策領域だと思いますので、何とか実働的な福祉避難所開設の体制を整えていただきたいと思います。
今回の教訓を基に、災害時の福祉関連施設の対応について、市として何か取組の方向性があればお聞かせください。
一例としまして、障害福祉分野におきましては、三浦市基幹相談支援センターが主体となりまして、市内各障害福祉サービス事業所にアンケートを発出し、その結果を題材としまして、自立支援協議会の障害福祉サービス提供事業所連連携部会で災害に対する対応を検討していくことを伺っております。
また、高齢者福祉分野におきましては、現在も市内4つの特別養護老人ホームと継続的に連絡会を行っておりますが、その中で対応を強化する取組を進めていく考えでございます。
理解をいたしました。

さて、(3)の『課題と今後の取組』に移ります。
一連の対応や体制について確認をしてまいりましたが、市としてこれまでの取組が実を結んだと思える点と課題が浮き彫りになった点の両方を伺いたいと思います。
今回の津波警報の発表に伴い、多くの方が高台へ避難されました。
また、避難場所となった小中学校では、避難者の受入れを教職員と避難してきた方が協力して行っていたとの報告も受けております。
これは、これまで防災訓練や防災講話、避難所運営委員会等の機会に自助・共助について周知していたことが浸透してきたものと考えております。
一方、津波警報の発表による避難行動において浮かび上がった安全な経路への誘導等の課題がありました。
また、避難所開設の時期、避難された市民の熱中症対策等についても、今後検討を行っていきます。
本当に地域のさまざまな方の行動やご尽力によって混乱が最小化されたと思っています。
これまで確認したとおり、行政の体制自体にも反省すべき点が大いにあったことは、謙虚に受け入れるべきだと思います。
もう対応の批判については最後にしますけれども、細かい改善点として、特に情報発信の取組に関しては、すぐにでも是正できるポイントが随所に見られたと感じています。
この指摘について、どのような認識かお聞かせください。
情報発信について、市のホームページに関しましては情報量が少なく、もっと目立つように掲載したほうが効果的だったと考えております。
また、防災行政無線の放送に関しましても、情報量が少なかったと考えております。
今回の事案を教訓として、今後、情報発信について、防災行政無線の放送に関しては、一定の時間継続的に避難指示を放送するほかに、さまざまな情報を分かりやすく伝えていくことに努めていきたいと考えております。
また、市のホームページの掲載については、トップページに目立つように掲載し、速やかにできるだけ多くの情報を掲載していくように努めていくべきと考えております。
特に公式LINEや防災メールにはファイルやURLの添付が可能なわけですから、高台に避難しろという指示だけではなくて、ハザードマップを添付して、今いる場所の状況を確認してもらう情報発信があってもよかったと思います。
また、近隣自治体と比べて、市のホームページのトップページに津波情報が掲載されたのも最も遅かったことを確認しています。
情報の質とスピードという観点で、すぐに改善できるよう庁内で動いてほしいと思います。
さて、今回の津波を受けて市民の防災意識の高まりを感じていますが、市としてこの部分についてどのような認識をお持ちか伺います。
今回の津波を受けまして、各区や団体から防災講話の依頼が増えております。
また、防災訓練を実施していなかった上宮田1区が訓練実施に向けて動き出しており、会議が開催されていなかった旭小学校の避難所運営委員会も会議の再開に向けて動き出している状況などを考えますと、今回の事案をきっかけに市民の防災意識が高まってきたと感じております。
ぜひこの流れを生かして、地域の防災への取組を全力でバックアップしていただきたいと思います。
これまでさまざまな問題提起を含めて議論を展開させていただきました。何が正しかったのか今も検討を繰り返している最中だと思いますが、行政の対応については、やはり他の自治体職員との意見交換が非常に重要になってくるはずです。
そうした場は既に、または今後設けられているのか伺います。
他の自治体との意見交換につきましては、横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センターの防災主管部長等で構成されております三浦半島地区広域防災対策推進連絡協議会が定期的に開催されておりまして、そのような機会に今回の対策等についても意見交換を行いたいと思っております。
ぜひとも意見交換を重ねた上で、今後の津波対応をどのように進めていくのかを市民にしっかりと伝えていってほしいと思います。
最後に、市長、今回の津波対応を受けて、ご自身や市としての今後の取組について何か思うことがあれば、総括として伺います。
市としての今後の取組としては、今回の津波警報発表に伴い実施した対応について確認し、避難所の開設については、周知方法、開設時期、運営等について、効果的な実施方法等について検討を行っております。
また、各公共施設における対応状況についても確認し、課題等については関係機関等とも協議を行ってまいります。
今後、同様の事案が発生した場合には、今回の事案を教訓に、適切な対応と適切な指示を行うよう今後努めてまいります。
インスタグラムの件も含めてですね、市長の職責として反省する部分も確認できたわけですけれども、今回最も検証すべきなのは、災害対策のトップである市長ご自身の対応だったと思います。
こと災害対応という側面において、政治経験がないこと、そして就任後間もないということは、絶対に言い訳にしてはなりません。
あなたの決断もしくは決断しなかったこと、その選択1つで多くの市民の命が危険にさらされ得るということを改めて自覚していただきたいと思います。
出口市長は市政の刷新や新しさに関心が強いようですが、本当に求められる市政の新しさとは、先人たちへのリスペクトの気持ちを忘れず、地道な過去の検証を踏まえて生み出されるものだと私は思っています。
例えば、2011年の東日本大震災の際の対応は本当に大切な教訓となると思います。
当時の市長や副市長、職員はもちろん、議会はどのような考えのもと動き、それがどのような結果をもたらしたのか、就任後に当時の状況をしっかりと把握し分析しようとしましたでしょうか。
その答弁はあえて求めませんが、ボーナスを全額返上する、全職員と面談をする、そんな一見キャッチーな取組をする前にやらなければならないことがたくさんあるのではないでしょうか。
私としても今回の対応の教訓を1つにして学び続けていく所存ですので、この部分の積み重ねをどうかよろしくお願いします。
2.子育て支援(未就学児)の取組と今後

それでは、2番、子育て支援の取組と今後にテーマを移します。
2人のこどもを育てている子育て世代の当事者として、これまでにも子育て支援については数多くの質問・要望を行ってきました。
その要望の裏には多くの市民の方の声が含まれているわけですが、行政としてもそうした声を真摯に受け止め、限られた財源の中で子育て支援の拡充に向けて動いてくださっていると認識をしています。
今回、改めてそんな子育て支援事業の状況を確認させていただき、よりよい施策実現のために議論をさせていただきたいと思います。
なお、子育て支援の対象は幅広いですが、深く議論をするためにも、今回は未就学児までの支援に絞って質問を展開しますので、よろしくお願いします。
まず初めに、(1)妊娠~出産前の支援に入ります。
毎度このテーマの冒頭で確認していることですが、本市の出生数の推移についてお聞かせください。
本市の出生数でございますが、令和4年度は137人、令和5年度は120人、令和6年度は129人となっております。
年度によるぶれや誤差があることを考慮しても、令和6年度の出生数が前年度と比べて上がったというのは喜ばしいことだと思います。
さて、妊娠から出産までの時系列に沿って各施策を確認してまいります。
まずは、妊娠のタイミングです。
妊娠届出時には母子健康手帳や妊婦健康診査受診券等を交付しているかと思いますが、妊婦本人への面接の実施率について伺います。
妊娠届出時の妊婦本人への面接実施率は100%となっております。
母子健康手帳交付時には体調不良等で、家族が来所し妊婦本人に面接をできなかった場合にも、後日、保健師や助産師等による面接を必ず実施しているところでございます。
妊婦さん本人が妊娠の届出のために来所できなかった場合であっても、しっかりとアフターフォローができているということです。
母子保健法に基づく公的な事業として妊産婦訪問指導事業があります。
これは、健康診査で保健指導が必要と判断された妊産婦の家庭を訪問し、健康状態の確認、妊娠・出産・育児に関する相談や指導を行うものです。
妊娠・産後は、体調の変化や、心身の不安を抱えやすい時期であり、安心して過ごすための支援としてとても大切になる事業です。
そこで、本市の妊産婦訪問指導の実施状況について伺います。
妊娠中には必要に応じまして訪問を実施しております。
妊娠8か月児にはアンケートも実施し、希望や必要に応じて面接や電話連絡を行っており、アンケートに回答がなかった場合にも妊婦健診の受診状況を確認する等、全ての妊婦の妊婦経過を把握するようにしております。
産後は、新生児訪問と同じタイミングで産婦に訪問を実施しておりますが、里帰り中の場合は、里帰り先の市町村に対し訪問を依頼するなど、全ての妊婦に対応しているところでございます。
保健指導が必要な場合だけでなく、一定の期間で妊婦さん全員に対してアプローチを行っていること、そして、里帰り出産をする市民に対してもしっかりとフォローを行っていることが分かりました。
いろいろと不安の多い産前・産後の時期に顔見知りの親切な担当職員さんが話を聞いてくれたことは、当時、私も私の妻も非常に心強く思っておりました。
こうした妊婦さんと担当職員の顔の見える関係というのは、小さいまちである本市の子育て支援の強みでもあると感じています。
さて、その他に母子保健法に規定された事業としては、母親・父親教室があります。妊娠期や産後の心身の変化を理解し、子育ての準備を進める場として重要な役割を果たしています。
本市におけるこの事業の具体例として、市内在住の妊婦さんとそのご家族やパートナーを対象にしたプレママパパ体験Dayがあります。このプレママパパ体験Dayの参加者の推移と、妊婦さんの家族の参加状況を伺います。
プレママパパ体験Dayは年3回実施しておりまして、各回8組程度の参加となっております。
そのうちのですね、父親の参加率は8割程度で、そのほかに祖父母やきょうだい児が参加することもございます。
参加者からは、実際に赤ちゃんの人形をお風呂に入れる沐浴体験や父親の妊婦体験が好評で、子育ての準備や、家族に妊婦の大変さを知ってもらう貴重な機会となっております。
まさに私もちょうど3年ほど前になりますが、妻の初めての出産を前にこのプレママパパ体験Dayに参加させてもらいました。
あのとき学んだ沐浴のやり方は下の息子の沐浴のときも忠実に守っていたぐらい、本当に有意義な時間だったと今でも思います。
一人でも多くの方にこのプレママパパ体験Dayに参加してほしいところですが、現状、このイベントは年3回、土曜日の開催で固定されています。
土曜日にお仕事があるご家族も少なくないと思いますが、開催日に参加できない方への対応はどのように行われているのかお聞かせください。
保健師、助産師等が訪問により対応しておりますが、休日もできる限り対応している状況でございます。
個別対応も行っているとのことで安心をしました。
ぜひその対応を継続していただきたいと思います。
さて、次に行きますが、今年度より、もともと市が行っていた妊婦さん・みうらっ子応援ギフトが三浦市妊婦のための支援給付に名称変更されました。
本事業の名称を変更した背景と目的について伺います。
これまで出産・子育て応援交付金事業として実施してきました妊婦さん・みうらっ子応援ギフトの代わりに、法的事業として妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業が新設されました。
子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付、児童福祉法に妊婦等包括相談支援事業が位置づけられ、事業を効果的に組み合わせて行うよう子ども・子育て支援法に規定されております。
妊婦さん・みうらっ子応援ギフトは妊娠期から低年齢期までの子育て世帯を対象としておりましたが、妊婦のための支援給付は妊婦を対象としており、妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、安心してこどもを産み、育てることができる環境を整備するものでございます。
支援の方向性を妊婦さん、お母さんによりフォーカスする意味で名称を変更したということです。
この名称変更に伴い、給付対象の条件に変更があったのかを伺います。
妊婦さん・みうらっ子応援ギフトの対象者は、1回目が妊婦、2回目は出生したこどもの養育者でありましたが、妊婦のための支援給付の対象者は2回とも妊婦となります。
また、妊婦のための支援給付では、1回目は妊婦届出後、2回目は胎児の数の届出後に支給するため、これまで対象とならなかった流産・死産等の場合も寄附を申請することができるようになっております。
結果的に以前よりも給付の対象が広がったことを理解しました。
お聞きするのが大変忍びないのですが、実際に流産・死産等をされた方からの申請はあるのでしょうか、伺います。
令和7年7月末時点で8件の給付申請がありまして、支給をしているところでございます。
流産や死産で大切なお子様を亡くされた悲しみは計り知れないものがあります。
市として、そのような境遇のお母さんやご家庭に対し、何かサポートができているのか伺います。
保健師等が可能な限りご本人と面接を行い、心身の健康状態を確認するとともに、寄り添いながら話を伺っているところでございます。
また、面接が難しい場合には、電話での対応ですとか、ご家族から話を伺うことをしております。
必ず状況を確認しているところでございます。
積極的なアプローチをすることが絶対的に正しいと言えるのかは悩ましい部分もありますが、つらいお気持ちや悲しみを抱えたまま誰にも相談することができない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この地でこどもを産もうとしてくださったお母さんとそのご家族の無念のお気持ちへの寄り添い、いわゆるグリーフケアについては、引き続き真剣に取り組んでいただきたく思います。
また、赤ちゃんを亡くしたご遺族の方々へのケアだけではなくて、社会全体の意識を変えていく働きかけも重要だと感じています。
医療が発達した現代社会においても、妊娠すれば誰でも健康な出産を終えられるわけではありません。
妊娠が成立しても、約6~7組に1組は流産を経験し、死産については100組に1組も起こり得るとするという統計もあります。
決して他人事ではないこの現実をしっかりと社会全体認識してもらう活動も、ご遺族のお気持ちに寄り添うための大切なアプローチであると考えています。
来月10月9日から15日の1週間は、亡くなった赤ちゃんとご家族に思いを寄せるベイビーロスアウェアネスウイークの期間でもあります。
これは国際的な啓発週間であり、世界中の人々が気持ちを1つにし、亡くなった赤ちゃんやそのご家族に思いを寄せる取組です。
お隣の横須賀市でも、この期間に合わせて、シンボルカラーのライトアップやメッセージの投稿、啓発資料の掲示などが行われています。
本市においても、この地でこどもを産もうとしてくださったお母さんとご家族に対し、市民全体で思いをはせられるような取組があってもいいのではないでしょうか。
政策提言としてご検討をよろしくお願いします。
さて、過去の一般質問において、妊産婦タクシー利用助成事業の分析と検証を何度も求めてまいりました。
この事業は、妊産婦に対し計1万円分のタクシー利用券を支給するものです。
直近の答弁では、その分析を行うために、乳幼児健診において妊産婦タクシー利用券に関するアンケートを実施するとのことでした。改めて、アンケートの趣旨や目的について伺います。
妊産婦タクシー利用助成事業は、令和3年4月に妊娠中や出産後の母体への負担や経済的負担を軽減するために開始したものであり、4年が経過しております。
本事業の効果を検証する必要があると考えております。
そのため、乳幼児健診の会場におきまして、これまで妊産婦タクシー利用券を交付した保護者の方に対し、利用状況アンケートを実施することとしております。
アンケートの内容といたしましては、妊産婦タクシー券の利用状況や利用目的のみならず、妊産婦健診受診時や出産時に使用した移動手段、家族等からの支援状況を調査する内容となっております。
利用状況アンケートの集計結果で、現時点で公表できるものがあればお聞かせください。
令和6年度実施分につきましては、122人の方に回答を頂いております。主な集計結果についてご説明させていただきます。
利用状況は、妊産婦健診や出産が33%、レジャーや買物が19%、こどもの予防接種や受診等が16%、使用しなかったが27%、そのほかは5%でありました。
また、出産時の移動手段につきましては、自家用車や親類・友人の支援を受けた人が86%で最も多く、タクシーを利用した人は9%でありました。
また、意見としましては、タクシー券を利用できる期限を延ばしてほしい、券の枚数を増やしてほしい、心強かったなど、多岐にわたっております。
妊婦さんの健診時や出産時だけではなくて、幅広い使い方がされているということです。
また、出産時、つまり陣痛が起こった際のタクシー利用が9%という数値も大変興味深いと思います。
利用状況アンケートの結果を踏まえ、現時点で今後の本事業の方針を検討しているのか伺います。
出産時には多くの方が親族や友人の支援を受けながら分娩施設に移動している中、タクシーを利用している方も一定数おります。
いざというときに親族からの支援が受けにくい方のために、令和7年度の集計も進めながら、今後の支援策を検討していきたいと考えております。
タクシー助成事業自体の着眼点はすばらしいと思いますが、もし継続するのであれば、期限や使用条件、金額をしっかりと見直してほしいと思います。
また、ちょうど1年前の定例会でも提言しましたけれども、市内に産科がない、市内で分娩ができない本市の状況を踏まえ、陣痛が起こった際に自己負担なくスムーズに産科に行けるような移動支援施策は確立すべきだと思います。
特に近くに親族も頼れる方もいない中で出産をしなければならないご家庭にとって、陣痛がいつ来るのかという不安は計り知れないものがあります。
私が最も効果的かつ現実的だと考える陣痛時の移動支援がタクシー利用の全額償還です。
もちろんタクシーが配荷できる時間帯という条件下にはなりますが、陣痛で病院に行く際、躊躇なくタクシーを呼べるように、病院までのタクシー代に加えて、車内で破水・出血してしまった場合のクリーニング代等も含めて市が負担をするというスキームです。
使った分だけ請求される償還事業であれば、実務的なコストも最小化できるというメリットがあります。
もちろん仮にこうした事業が新設されたとしても、先ほどのアンケートの回答でもあったように、大多数の方は自家用車や親類・友人の支援を受けることになるのかもしれません。
しかし、タクシー利用という選択肢も加わることは、妊婦さんやご家族の心理的負担を大きく解消してくれるはずです。
具体的な政策提言として、陣痛タクシーの無償化をご検討ください。

さて、続いて、(2)の新生児~幼児期の支援に移ります。
赤ちゃんが生まれてからの代表的な支援に産後ケア事業があります。
これは、出産が終わったばかりのお母さんとお子さんを対象に、産後の体調を整えたり、育児の不安を解消するための事業です。本市の産後ケアには、宿泊サービス、デイサービス、訪問サービスの3つがあり、産後4か月未満であれば、申請により誰でも利用できるとされています。
この事業については、過去の一般質問でも確認しておりましたが、訪問サービスが比較的安価で利用の多い一方で、宿泊サービスとデイサービスは令和4年度から令和5年度まで利用実績がなく、その運用に課題を抱えていたかと思います。
この2つのサービスについて、令和6年度以降の利用実績に動きがあったのかを伺います。
宿泊サービスは、令和6年度に延べ4件、令和7年度8月末時点で延べ12件の利用がございました。
デイサービスにつきましては、令和6年度に実績はありませんでしたが、令和7年度に入ってから1件の利用がある状況でございます。
宿泊サービスは利用が急増し、デイサービスも利用が出てきたということです。これらの要因についてどのように分析をしているのか伺います。
宿泊サービスにつきましては、令和7年度より国の補助金を利用して、自己負担額を1泊2日1万8,000円から1万3,000円に引き下げたことが利用のしやすさにつながっていると考えております。
デイサービスにつきましては、現時点では令和7年度1件の利用ではございますが、利用できる時間を延長したことや食事つきとなったことで、今後の利用拡大につながることを期待しているところでございます。
まさに宿泊サービスについては自己負担額の高さ、デイサービスについては食事提供なしで4時間の枠という使い勝手の悪さについて、市民の方の声を代弁する形で私も改善を求めておりました。
こうした声をしっかりと反映していただいた結果なのかなと思います。
また、市のホームページの産後ケア事業の項目が今年度に入って一新されたことも、利用が高まったもう一つの要因として挙げられるのではないでしょうか。
このあたりの意図や狙いについてお聞きいたします。
事業の内容を見直したこともあり、産後ケアの種類と自己負担額につきまして、サービスごとの利用時間や内容が一目で分かるよう表にまとめております。
実施施設につきましては、これまで個別に案内をしておりましたが、ホームページに一覧を掲載することで、利用希望者がより具体的なイメージを持ってサービスや実施施設を選択しやすいように工夫をしております。
この工夫による効果は本当に大きいと思います。特に当該ページで申請の前から実施施設が把握できるようになったことは、産後でさまざまな不安を抱えるお母さんが利用を検討する上で大きなプラスになっているはずです。
改めて、産後ケア事業の改善、ひいては産後のお母さんと赤ちゃんに寄り添う支援の拡充に取り組んでいただき、本当にありがとうございます。
都心の比較的大きな自治体では、産後ケアを申請するまでのハードルが高く、また、ニーズの集中で枠がいっぱいとなり、なかなかサービスを受けられないという声をお聞きしたこともあります。
そう考えると、この産後ケア事業の拡充は、本市の子育て支援の強みにもなり得ると思いますので、引き続き積極的な取組をお願いいたします。
さて、本市の乳幼児支援という観点に立つと、もう一つ大切になってくるのが乳幼児健康診査の事業です。
これは市が無料で実施する集団健康診査の事業になりますが、この乳幼児健康診査の受診率の推移と未受診者への対応方法についてお聞かせください。
本市の乳幼児健康診査の受診率はおおむね90%以上で推移しております。
未受診者に対しましては、家庭訪問や所属の幼稚園・保育園等への確認により状況の把握を行っております。
未受診者に対するフォローは、引き続きしっかりと行ってほしいと思います。
母子保健法に基づく市町村が義務として実施しなければならない健康診査は1歳6か月健診と3歳児健診の2つになりますが、本市ではこれらに加えて、3か月児、10か月児、歯科健康診査ではありますが2歳児、そして、5歳児のタイミングで健康診査が行われています。
特に5歳児健診については、令和6年度から実施された比較的新しい施策になります。
この5歳児健診を追加した経緯や実施状況について伺います。
5歳児健診を開始するまでは、3歳児健診が就学前最後の検診でありました。
5歳児は、精神発達、言語発達、社会性の発達といった面で成長が著しく、この時期に発達段階における課題の有無を把握することで適切に就学準備を進めることができるため、国が5歳児健診の実施に係る費用助成を開始したこともあり、本市でも実施することとしました。
本市では、児童発達の専門医師の協力を得て、集団検診で実施をしております。
健診に慣れたスタッフが、より丁寧にこどもの様子を見ることができている状況でございます。
また、本市の人口規模だからこそ、ふだんから幼稚園・保育園や教育委員会などとの連携が図れ、支援を行う体制づくりができているため、5歳児健診におきましても、三浦市ならではの支援体制が図られていると考えております。
実際に健診後に必要な相談や支援につながった事例もあり、5歳児健診を受けたこどもの保護者からは、3歳児健診から就学までの期間に健診を受けられてよかった、こういった感想も聞いているところでございます。
確かに3歳児健診から次の就学時健康診断までには結構なスパンがありますから、市が5歳児のタイミングで発達について関わることができる機会は非常に貴重だと思います。
実際にこの短期間でも成果が出ているとのことで、国の助成をうまく活用しながら、この部分に寄り添った施策を打ち出したことを純粋に評価したいと思います。
この5歳児健診というのは他の自治体でも多く実施されているものなのかお聞かせください。
5歳児健診は国の補助対象であり、支援が強化はされているものの全国的には実施率は低く、県内でも実施している自治体は限られております。
さらに、集団検診として実施している自治体は珍しく、本市に他の自治体から視察に来るケースもございます。
先ほどの答弁にもありましたが、この5歳児健診1つ取っても、大きな自治体ではなかなか実施が難しい、コンパクトな本市ならではの支援体制だと言えるのだと思います。
こういったなかなか当事者にしか分からない、かゆいところに手が届く本市の子育て支援は、キャッチーさには少々欠けるかもしれませんが、本市の子育て施策における大切なセールスポイントだと思います。
引き続き、三浦独自の子育て支援の強みを拡充させていくことを要望します。

さて最後の項目となりましたが、(3)令和7年度新規の取組に移ります。
まず注目すべきなのは、今年7月に開所したあすカルみうらについてです。
この事業は、ご家庭において一時的に保育ができないときにお子様をお預かりするサービスです。
以前から一時預かりの拡充について多くのご要望を頂いていた私としても、開所に踏み切ってくださり、大変うれしく思っておりました。
7月の開所から約2か月が経過しましたが、これまでの利用人数、登録者数等の利用実績について伺います。
利用の延べ人数でございますが、7月が14名、8月が33名、利用延べ時間数は、7月が37時間、8月が127.5時間となっております。
また、8月末時点での利用登録者数は39人となっております。
正直もっと利用が多いものと予測しておりましたが、認知が広まるのはこれからなのかなと思います。
利用区分として、通常の一時預かり枠、いわゆるフリーで預けられるA利用と保留児童対策として保育園に入れなかった児童を一定期間継続して預かるB利用を設定しているかと思いますが、それぞれの具体的な利用内容について、改めて伺います。
A利用につきましては、保護者のリフレッシュなど、理由を問わずに一時的な預かりを行うもので、1か月に14日以内の利用を要件としております。
B利用につきましては、保育園などの入所申請中で保留となっている場合に利用可能な枠でございまして、原則1か月25日以上、1日4時間以上の利用を要件としております。
利用料金は、A利用が1時間当たり600円、B利用は1時間350円となっております。
内容について理解をしました。
利用のためには事前の登録が必要だと思いますが、具体的に利用に至るまでにどのような手続が必要かお聞かせください。
まず、予約システムへの利用者登録を行い、登録後、システムより希望する日時に面談予約を入れ、事業者と面談を行っていただきます。
面談後は、予約システムに表示される空き状況を確認して、システムに予約を入れた上で利用をしていただくようになります。
登録の際の面談は必須であるということです。予約システムを使い、スマホで利用申込みができるのはとてもいいことだと思います。
さて、B利用については、保留児童の解消を目途として設けられた仕組みであり、特にあすカルと同じエリアである小羊保育園の偏在がすさまじい中で、その活用が期待されています。
この2か月間でB利用の利用人数がどれぐらいあったのか伺います。
B利用につきましては、8月から1名、9月から1名が利用を開始しており、現在2名となっております。
また、今後の利用に向けた相談を数名から受けている状況でございます。
現時点での利用の実績を聞くと、もう少し利用があってもよいのではないかなとも思いますが、逆にB利用が増え過ぎるとA利用の枠も厳しくなるわけで、なかなか難しいかじ取りが求められることになると思います。
いずれにせよ、まだ始まったばかりの事業であり、今後定着して利用者が増えていくことを期待したいと思います。
今後、認知度を上げていく取組はどのように考えているのかお聞かせください。
SNS、ホームページ等での周知は継続して実施していきたいと考えております。
また、多くの方に事業所を知っていただくため、10月にこどもと一緒に自由に見学できる開放日を設ける取組について、現在検討しているところでございます。
開放日の設定はとてもいいと思います。やはり預ける側の親御さんとしても、どのような環境でこどもが過ごすのかというのが一番気がかりなところです。
そうしたお気持ちに寄り添うためにも、ホームページに預かり空間や遊具の紹介などをもう少し細かく掲載したり、動画を活用して紹介することも効果的なのではないでしょうか。
もう1点、預ける際の懸念の一つとして、現状ではお昼にまたがった場合に食事提供を行っておらず、持参が必要であることが挙げられます。この食事提供について今後どのように考えているのかを伺います。
現在、食事提供を行っている一時預かり事業所もあり、ニーズに応じて事業所を選択していただいているというふうに認識をしております。
今後、利用者の意見をお聞きする中で、食事提供を求めるご意見が多くあった場合には、対応を検討する必要があるというふうに考えております。
乳児期ですと食事のキットなどは市販品でも充実していますが、やはりその時期を超えてくるとお弁当作りが必要なってくるというところです。
スキームの構築は簡単ではないと思いますが、あすカルの認知や利用が拡大し、その中で食事提供のニーズが高まった際には、その実施もしっかりと検討していってほしいと思います。
せっかく立ち上げてくださった事業に対して細かい追加要望するのも少々心苦しいのですが、とにかく厳しい財源の中で、一時預かり事業の拡充に踏み切ってくださったことについては本当に感謝をしています。
実際に始めたからこそ把握できるリアルなニーズなどもあるはずなので、今回の事業を一時預かりだけの観点ではなく、子育て支援全体に関わる面でのアプローチとして有効に活用していってほしいと思います。
さて、もう一つの新規事業として、病後児保育についての新たなアプローチが挙げられます。
そもそもこの病後児保育事業については、その目標が数年にわたり「運営方針の策定」となっていますが、その実績はあまり見えなかったように思います。
この政策領域について、これまでの取組の経過についてお聞かせください。
令和4年度には、乳児健診時に病児・病後児保育事業に関するアンケートを実施したほか、神奈川県が実施しました病児保育事業の実態調査により、県下の状況や課題を把握しております。
令和5年度には、病後児のこどもを預かることができる仕組みとしまして、ファミリー・サポート・センター事業において病後児の預かりを開始しております。
令和6年度には、子ども・子育て支援事業ニーズ調査におきまして、こどもが病気になった際の対応に関する設問を設けまして、病児・病後児保育へのニーズの把握を行ったところでございます。
私の僅かな育児期間を振り返っても間違いなく病児・病後児保育のニーズはあると思うのですが、その対応を事業化するとなると、子育て支援の領域では使うべきではないかもしれませんが、費用対効果、税配分の効率性として大変な難しさがあると思います。
その中で、令和7年度は補助事業を開始するとのことでしたが、どのような事業を行うのか伺います。
令和7年度の新規の取組といたしまして、病児・病後児保育施設等を利用した場合の利用料を助成する事業を開始するところでございます。
具体的には、市外にある病児・病後児保育施設を利用した場合や、病児・病後児を預かるベビーシッター、ファミリ・ーサポート・センター事業による病後児預かりを利用した場合についても助成対象としております。
助成額は、1回の利用につきまして3,000円を上限とし、連続して利用する場合は5日を限度として利用可能とするものでございます。
市外の施設利用、そして病児・病後児におけるベビーシッターやファミサポ利用への助成ということで、かなり現実的な施策を打ち出してくださったと感じています。
1回につき3,000円の助成という金額も妥当性があると思います。
市外にある病児・病後児保育施設の利用を想定しているとのことですが、病児・病後児保育を実施している施設であればどの施設も利用間可能と考えてよいのでしょうか、お聞かせください。
市外の施設で市が運営主体となっている場合など、利用対象をその市に在住している市民に限定しているところもあるため、全ての病児・病後児保育施設が利用できるということではございません。
市外在住であっても施設の利用が可能かどうかを確認した上で利用していただくよう、周知していく必要があるというふうに考えております。
今後、利用状況を追いながら、利用可能な施設、すなわち利用の選択肢が増えることを願っています。
本事業については、今後どのように周知を行っていくのかお聞かせください。
令和7年10月号の「三浦市民」に掲載を予定しているほか、SNS、ホームページ等での周知を予定しております。
また、新生児訪問や乳幼児健診時などに対象者に直接チラシを配布することも想定しております。
こちらの事業についても、あすカル同様、期待をしています。
今や自治体が子育て支援を強化するのは当たり前となった感すらあります。
財源の豊かな不交付団体や過疎地域等を対象とした国の交付金を活用できる自治体を羨ましく思う気持ちも正直あります。
お財布事情という面ではなかなか厳しい本市ではありますが、三浦の住環境だからこそできる豊かな子育てがあると信じています。
これまでも確認してきたとおり、三浦ならではの子育て支援の強みもあります。
悲観的な声があるのも事実ですが、私が議員となってからのこの僅かな期間だけ見ても、本市の子育て支援は本当によくなってきていると思います。
知恵を絞りながら現場で奮闘している職員に敬意を表しつつ、子育て世代の代表として、引き続き、しっかりと市民の声を聞き、現実的な施策に落とし込んで提言を行ってまいります。

以上で私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。