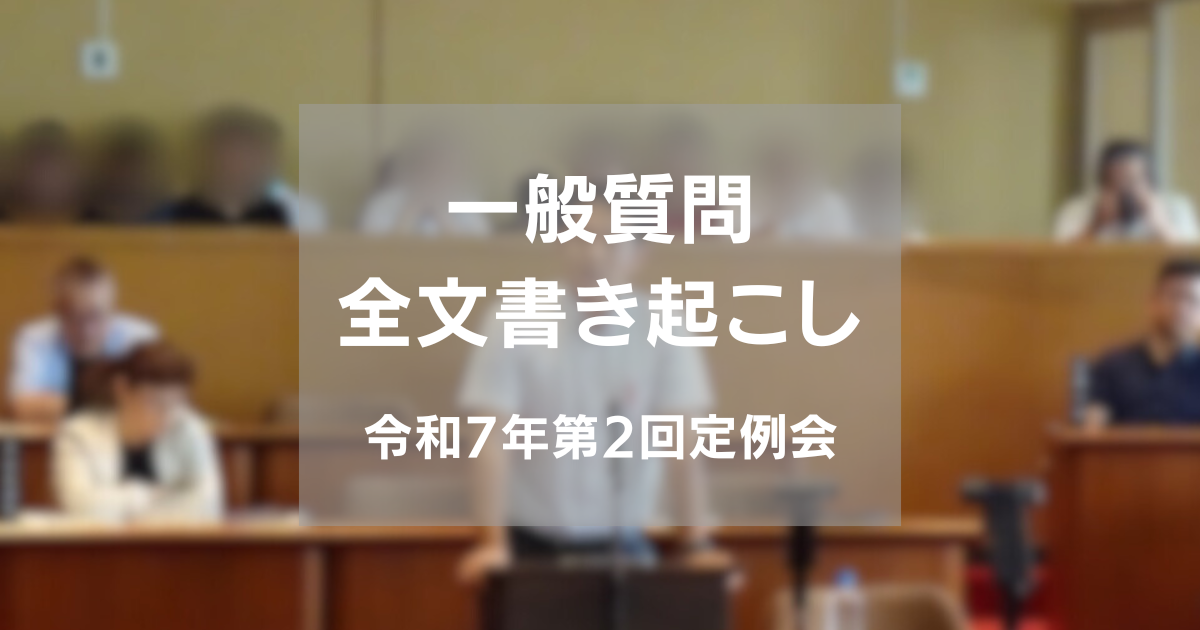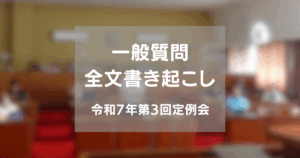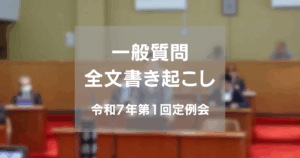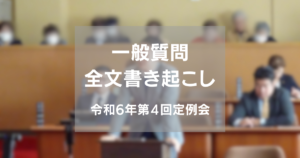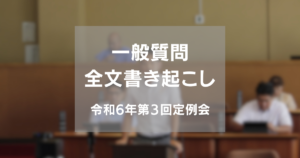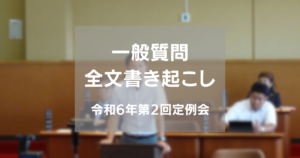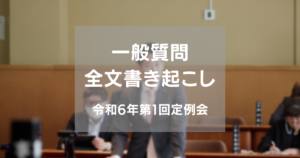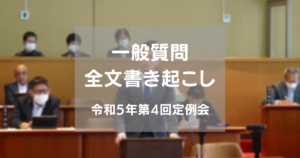令和7年第2回定例会のうち、7月14日に行われた一般質問について、私が書き起こした全文をアップします。
一般質問については、以前の投稿(初めての一般質問を終えて)で概要をご説明しておりますので、よろしければご覧ください。
※展開がわかりやすいように、吹き出し風の文章を適宜挿入します。
※行政からの答弁については、青い囲み文字で記します。
※議場での発言には議長の許可が必要なので、実際には議員、職員ともに発言ごとに挙手→議長からの許可の流れがありますが、ここでは便宜的に省略します。
「一般質問なんて聞いたことがない」
「聞いていてもつまらない」
そんな感想をお持ちの方も少なくないと思います。
私としてもそのお気持ちがよくわかるので、手元に資料がなくても話の流れがつかめるよう、構成や原稿はできる限り工夫しております。
市長が変わって初めての一般質問ということもあってか、たくさんの傍聴者がいらっしゃいました。
YouTubeの再生数もこれまでの定例会とは比べ物になりません。
既に色々なご意見をいただいておりますが、あらためて感じたこと、思ったことなど教えていただけたら幸いです。
※発言の内容は下記の通告書通りになります。
1.自治会運営の現状と今後について
(1) 自治会組織の実態
(2) 行政の役割と支援
(3) 自治会運営の課題認識
(4) 今後の取り組み
2.新市長の公約と認識について
(1)新市長の公約と認識について
※クリックすると該当部分にジャンプします(画面右下の矢印ボタンで最上部に戻れます)
下記の文章はあくまで私がYoutubeでのアーカイブ配信を個人的に書き起こしたものであり、正式な議事録ではありませんのでご了承ください。
議事録がアップされましたらこちらにそのリンクを追記する予定です。
【追記】議事録が公開されたため、下記にリンクを記載します。
※令和7年第2回定例会→第3号 7月14日の順にクリックで閲覧できます。
以下発言

ただいま議長の許可を頂きましたので、三志会の一員として質問をさせていただきます。
質問は発言通告どおり、1番、自治会運営の現状と今後について、2番、新市長の公約と認識についての2点となります。
一問一答方式で質問をさせていただきますので、ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。
1.自治会運営の現状と今後について
まず初めに、『自治会運営の現状と今後について』を取り上げます。
前提として、地域社会の基盤とも言える自治会について、少し整理をしたいと思います。
なお、自治会や町内会など、同様の地域コミュニティを指す言葉は幾つかありますが、ここでは便宜上、自治会に統一してお話を進めさせていただきます。
自治会とは、法律に基づいて設立される団体ではなく、地域住民が任意に結成する自主的な組織です。
もともと地縁に基づいて形成された民間の自治組織として、親睦活動や地域課題の解決、さらには行政の協力体としての役割を担いながら、長年にわたり地域社会を支えてきた枠組みです。
防災や防犯、清掃活動、地域行事などに加え、近年では、災害時の安否確認や孤独死の防止、認知症高齢者の見守り、こどもの安全確保、空き家管理といった新たな課題にも対応が期待されています。
一方で、人口減少や高齢化、ライフスタイルの多様化といった社会の変化により、自治会への加入率は低下し、担い手不足や非加入世帯とのトラブルなど、活動の持続性に関わる深刻な課題も各地で浮き彫りになってきています。
全国的には実際に解散を余儀なくされる自治会も増えており、もはやこの状況を見過ごせる状態ではないのかなと思います。
私自身も本市にUターンしてきてから、議員というよりは一区民として自治会に加入する中で、役員の皆さんをはじめとする現場の方々の並々ならぬご尽力に触れてきました。
同時に、その運営が、持続可能性という観点において非常に厳しい局面にあることを実感しています。
そこで、今回は、自治会運営の現状と今後について取り上げ、市内における自治会組織の実態を確認した上で、行政の果たすべき役割や支援の在り方、さらには現場が直面する課題と今後の方向性について、提案を交えて伺ってまいります。
まず初めに、三浦市では区長の組織体として区長会があるかと思いますが、現在の区の数を伺います。
三浦市区長会は、現在54の区で組織されております。
区と自治会の形態が完全に一致していない場合もあるかと思いますが、おおむね区を単位として自治会が構成されており、三浦市区長会はそうした54区で組織をされていると理解しました。
続いて、直近で把握している市内自治会の加入率についてお聞かせください。
令和7年4月時点の加入率は、93.8%となっております。
令和3年7月、総務省は地域コミュニティに関する研究会を設置しました。
その中で行われた全国1,741市区町村を対象にした自治会等に関する市区町村の取組に関するアンケート取りまとめ結果によれば、回答のあった市区町村のうち、直近の令和3年で、自治会加入率が90%以上あった自治体というのは僅か14.7%でした。
その数字から相対的に考えると、三浦市は比較的自治会加入率の高い自治体であると言えるのかなと思います。
ちなみに、もう少し長いスパンで見たときの加入率の推移はどうなっているのかについても伺います。
手元にある一番古いデータは、平成20年の92.3%となっております。
それ以降はおおむね92%から96%の間で推移しており、最近の3年間は、令和5年が95.4%、令和6年が95%、令和7年が先ほど申し上げた93.8%となっております。
長いスパンで見ると完全な減少トレンドとは言えないものの、直近3年間だけで見れば、多少なりとも減少傾向が見られるのかなと思います。
ちなみに、先ほど引用した同アンケートでは、直近10年間にわたり継続的に調査を行っている自治体を対象に、自治会加入率の平均的な推移も分析されています。
これによると、人口規模の大小にかかわらず、全国の市区町村における自治会加入率について、この10年間でおよそ7%前後の減少が見られており、注目すべき傾向だと感じています。
ちなみに、市内のエリアによって自治会の加入率の高さに偏在性があるのか、傾向の把握や分析を行っているのか伺います。
市では大字町ごとの世帯数を公表しておりますが、自治会の区域は大字・町の区域と異なっているところも多くあり、これまで自治会の加入率を地区ごとなどで分析したことはございません。
今後の政策的アプローチを考える上でも、地域ごとの傾向を把握しておくことは重要だと思います。
しかしながら、これまでにそのような分析は行われていないということです。
さて、自治会の中には、いわゆる認可地縁団体として市長の認可を受けて活動している団体もあるかと思います。
本市において現在この認可を受けている自治会は何団体あるのか確認させてください。
三浦市の認可地縁団体は、37団体ございます。
先ほどの区長会の構成と照らし合わせると、少なくとも半分以上の団体が認可地縁団体であると思われます。
この認可地縁団体としての認可を受けると、どのようなメリットがあるのかを伺います。
地縁団体として市長の認可を受けると、法人格を有することとなります。
特に地縁団体が区民会館などの不動産を所有している場合には、法人格を有すると法務局で土地家屋の所有に関する登記を行うことができることから、不動産の権利関係を明確にすることができます。
そのほか、金融機関での口座作成や収益事業を行う場合の契約関係などについて、法人格を有することでスムーズに行うことができるものと認識しております。
認可地縁団体であるか否かによって自治会の価値や存在意義が変わるわけではありませんが、この認可を受けると自治会に法人格が生まれ、契約や実務において優位性が生まれるということです。
ここで改めて、市は自治会に求められる役割についてどのように考えているのか伺います。
地方自治法では、市長が支援団体を認可する要件の一つとして、団体の目的が「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこと」とされております。
自治会にはそのような活動を行うことが求められていると認識しております。
まさにその役割のもと、自治会は長年にわたって地域のつながりを支え、様々な活動を担ってきたわけです。
そこで改めて、市として把握している範囲で、自治会が実際に行っている活動内容についてお聞かせください。
区によって活動内容は異なりますが、市から区長会に委託している広報紙の配布や掲示板へのチラシ掲示などは、全ての区で行っております。また、防犯活動や交通安全活動、環境美化活動などを行っている区が多くございます。
それぞれの自治会の考えやニーズに応じてさまざまな活動が行われているということです。

さて、ここまでで自治会組織の現状について確認してまいりましたが、(2)行政としての役割と支援に入ります。
自治会の活動はあくまで住民による自主的なものであり、自治会は行政の下部組織ではないという前提に立ちつつも、日常的にさまざまな面で行政との連携・協力が行われています。
そこで、まず、こうした行政と自治会の関係性について、市としてどのような認識を持っているのかお聞かせください。
地方自治法では、認可を受けた地縁団体につきましても、地方公共団体の一部とすることを意味するものではないと規定されております。
認可地縁団体も含めて、自治会は独立した地縁による団体と認識しております。
一方で、地縁による団体というその特性から、広報や防犯活動などのさまざまな地域生活の場面で行政に協力をしていただいております。
答弁にもありましたが、大前提として自治会はその名のとおり住民による自主的な組織体であり、市から独立した存在です。
一方で、現実には協力関係として行政の取組を担っていただいている場面も多くあります。
その典型的・代表的なものとして、市からの広報紙等の配布業務があります。
これらの配布物については、自治会を通じ、実際にどのような流れで各世帯に届けられているのかお伺いします。
広報紙などの市からの配布物は、まず、運送会社によって各区の指定の場所などに搬送されます。
各区に届いた広報紙などは、市が三浦市区長会に委託をしている配布業務に基づき、各区で区長や役員の方などが仕分を行い、各世帯に配布されております。
具体的な配布の方法につきましては、各区によって異なりますが、隣組や班などの単位で各戸に配布したり、回覧のように回して1部ずつ受け取ったり、各区の実情に応じて配布していただいております。
委託による配布業務の流れについて理解をいたしました。
次にお伺いしたいのは、自治会の内部運営、特に名簿の作成や会計の方法についてです。
こうした情報は、それぞれの自治会が主体的に管理するべき内容である一方で、特に認可地縁団体の申請などの場面では、市と情報のやり取りをする機会もあるのではないかと思います。
市としてこうした名簿や会計に関して各自治会と何らかの関わりや働きかけを行っている部分があるのか、お伺いします。
自治会が認可地縁団体の申請を行う際には、構成員の名簿や現に地域的な共同活動を行っていることを記載した書類を添付していただくことになっているため、名簿や前年度の事業報告、収支決算などを添付していただいております。
ただ、名簿の作成方法や会計の方法などにつきましては、各区が実情に応じて対応していただいているものと認識しております。
市民部で区長会の事務局を担当しており、個人情報保護の観点から、自治会が会員名簿を作成する際の注意事項について区長会総会で資料を配付しておりますが、それ以外には各区の名簿の作成や会計などについて特に関わりはございません。
ここについても先ほど確認をしたとおり、自治会はあくまで独立した組織でありますから、注意事項の伝達等以外は各自治会に委ねているということです。
ただ、先ほども確認したとおり、自治会の協力によって成り立っている行政実務の部分も一定程度ある中で、市から自治会への補助金や負担金があってもおかしくないのかなと思います。
各自治会に対する補助金などの支援にはどのようなものがあるのか伺います。
自治会を対象とした補助では、主に一般財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業がございます。
コミュニティ助成事業は幾つかのメニューに分かれており、コミュニティ活動に必要な設備の購入等に関する一般コミュニティ助成事業、区民会館の建設に関するコミュニティセンター助成事業、自主防災組織として地域の防災活動に必要な設備の購入等に関する地域防災組織育成助成事業などがございます。
ほかに、基本的には自治総合センターのコミュニティセンター助成事業と重複して補助を受けられませんが、市が独自で行う区民会館建設補助がございます。
行政からの財政的な支援としてコミュニティ助成事業があるということです。
具体的な対象やメニューはさまざまですが、このコミュニティ助成事業の利用状況について、直近の実績をお聞かせください。
過去3年間では、令和4年度に松輪区がエアコン・備品の購入等で一般コミュニティ助成を、和田の里区が区民会館建設でコミュニティセンター助成を受けております。
令和5年度は助成を受けた区はございませんが、令和6年度に上宮田6区が蓄電池・蓄電池用のソーラーパネル等の購入で地域防災組織育成助成を受けており、令和7年度は油壺若草区が自治会館で使用する備品等の整備で一般コミュニティ助成の採択を受けております。
過去の予算・決算審査でも確認しておりましたが、実績について改めて理解をいたしました。
この助成金、申請したい気持ちがあっても、書類作成の煩わしさなどで申請に至らないケースもあるとお聞きします。
もちろんそこは各自治会の踏ん張りどころでもあるわけですが、市としても引き続き、メニューの周知や申請に際してのフォローには力を入れていただきたいと思います。
さて、各自治会の長の集まりとして区長会の存在があります。
この区長会の運営体制や役割について、改めてお聞かせください。
市内には、三崎、南下浦、初声の3地区にそれぞれ各地区の区長が所属する三崎町区長会、南下浦町区長会、初声区長会が組織されております。
また、各区の相互連絡や地域の繁栄、市民福祉の増進を目的として、市全体の区長が所属する三浦市区長会が組織されております。
三浦市区長会は、毎年春に理事会・総会を開催し、また、各区長が総務、広報、保健衛生・環境、教養、安全の5つの部会にそれぞれ所属して部会ごとの取組を行い、そのような取組の一環として区長会表彰や研修視察などを行っております。
三崎、南下浦、初声の各地区にはそれぞれ区長会があり、市全体でも三浦市区長会が組織されているということです。
この三浦市区長会が主催した企画として、令和4年度に実施された「すべて魅せます!三浦のふるさと54区知って写真館」があります。
この企画は、公益財団法人地域社会振興財団の令和4年度人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金を活用して行われたと認識していますが、後にこのような冊子にもまとめられています。
私が議員なる前、2年以上前の企画ではありますが、今でも印象に残るすばらしい取組だったと思っています。
先ほどのご答弁で区長会内部でさまざまな活動が行われていることは確認できましたが、区長会として恒常的に行われている広報や情報発信については、現状どのようになっているのかお伺いします。
過去には広報大会というイベントを行っておりましたが、区長会や各区の広報・情報発信という点ではあまり寄与しないという意見が多く、現在取りやめております。
最近では、広報大会に代わる広報活動として、令和5年度にみうら市民まつりに出展し、令和4年度に行った写真展に作成したパネルを展示して、写真集の配布を行いました。
また、令和5年度から6年度にかけてホームページをリニューアルしており、現在、ホームページの活用を含めて、今後の広報の方法などについて検討していると伺っております。
おそらくコロナという突発的な事象も含めて広報大会の在り方を検討されたのだと思います。
広報大会の取りやめに終始することなく、代替の広報活動を展開したことは高く評価したいと思います。
ホームページに関しては私も確認させてもらいましたが、枠組みというか、フロントページを作成したこともすばらしいと思います。
ここに関しては、今後、各区でページ作成を担える人材を確保していく必要があります。
ここまで自治会運営の意義や枠組み、行政との関係性や支援について確認をしてまいりました。

これらを前提に、本題とも言える(3)番、自治会運営の課題認識に移ります。
まず、全国的に共通する課題として、自治会を支える役員などの成り手不足や高齢化が挙げられます。
三浦市においても同様の状況があると認識していますが、市としてはどのように実態を把握しているのか伺います。
三浦市では、加入率はかなり高い水準を保っておりますが、役員などの成り手不足や高齢化についての課題を聞くことが多く、区長や役員を交代したくても、次にやってもらう人が見つからず、続けていただく方も多くいるように伺っております。
そのような状況もあり、一部の方に負担が大きくならないよう、1年や2年など年数を区切って順番に役員を行うことを決めている区もあると伺っております。
今の答弁にもあったとおり、役員さんの次のやり手がいないからやめられないという状況は、多くの自治体に共通する深刻な問題だと思います。
次の人に同じ苦労をかけさせたくないという気持ちからなかなか声もかけられず、結果的に同じ方が何年も役を担い続けるという悪循環に陥っているケースもあるのではないでしょうか。
運営上の負担の中でも、特に大変だと声が上がるのが会費の徴収です。各区がどのように自治会の会費を集めているのか、徴収方法の状況について、市として把握していることがあればお聞かせください。
会費の徴収も含めた自治会の運営につきましては、各区の実情に応じて行われており、全てを把握しているわけではありませんが、隣組や班の単位で現金で徴収しているという話を聞くことが多くございます。
ご不在の方の家に何度も足を運んでもなかなかお会いできないケースもあり、また、役員等の高齢化などもあり、負担が大きいと伺っております。
こうした個別訪問、現金徴収のスタイルは、徴収する側にとって負担が大きいというだけではなく、徴収される側、特に仕事などでなかなか自宅にいる時間を確保できない方にとっても、ご迷惑をおかけしてしまっているという気を遣う結果となり、双方にとってストレスのあるやり取りになっているのが実情だと思います。
また、全国的には自治会の集金を装った詐欺事件も起こっており、この徴収方法の見直しというのは、銀行振込や電子決済の活用も含め、しっかりと検討される必要があるかと思います。
また、同様に個別に足を運ばなければならないもう一つの代表的な業務が、先ほども確認しましたけれども、市から委託されている広報紙等の配布業務です。
今確認したとおり、市から三浦市区長会を通じて各区にこの業務が委託されているわけですが、過去の決算資料等を確認すると、この委託料として年間合計で約135万円が支出されています。
加えて、市役所から各区民会館等への配送料も別途市の負担になっているはずです。
いずれにしましても、本来的には行政が責任を持つべき業務でありながら、実際には区長会、そして各自治会の役員や担当者のご尽力によって支えられているというのが現状です。
そこで伺いますが、市が三浦市区長会への委託を仮に行わず、直接全戸に広報紙を配布する場合、どの程度の費用がかかるのか、これまでに試算をしたことがあるのか伺います。
近年、区長会への委託以外の配布方法につきまして、見積り等を取得して金額を確認したことはございません。
県内他自治体における自治会を介さない配布方法での費用を参考にしますと、ポスティングなどの直接全戸配布する方法は、現在の配布委託料より多くの費用がかかる見込みとなります。
そもそも他の配布方法での試算を行ったことがないということです。
私自身、定例会ごとに発行している政治活動用のビラをできるだけ多くの方に届けたいと考える中で、全戸配布の委託には相当なコストがかかることを痛感しています。
ましてや配布物が冊子になったり複数であったりすれば、そのコストはさらに膨れ上がります。
そう考えると、区長会への委託、すなわち各区の担当者のご協力、ご尽力によってこの支出が大きく抑えられていることになると推測されます。
だからこそ、結果的に自治会への委託、ご協力依頼を継続するにしても、自治会運営の負担軽減という観点からも、行政が担う場合の費用というものを一度試算しておくべきだと考えます。
この点についてここで提言をさせていただきます。
さて、広報紙の配布のように三浦市区長会を通じて市から委託している業務以外に、区長会や各自治会に対して依頼していることがほかにもあるのかお伺いします。
広報紙の配布以外には、主に、市と連携して地域で活動していただく各種委員の推薦等がございます。
民生委員・児童委員や青少年指導員、保健衛生委員など、様々な分野の各種委員の推薦を各区長に依頼しております。
また、市の設置している審議会や協議会などの委員に、三浦市区長会長や区長会から推薦された各区長に就任していただくことを依頼することもございます。
私も約3年前に三浦に戻ってきて以来、地域で活動されている委員や指導員の皆さんの姿を目にする中で、本当にきめ細やかな活動で地域を支えてくださっているなということを実感してきました。
こうした人材の推薦や連絡調整といった業務は、仮に市が全てを担うとなれば、莫大な労力と人的コストがかかるのは明らかです。
また、直近でいえば、今年度は国勢調査の年ですけれども、この調査員の推薦業務もまた、自治会役員にとっては非常に大変な業務だと聞き及んでおります。
ここまで自治会運営に関するさまざまな課題を見てまいりました。
この課題の背景には、少子高齢化やライフスタイル・考え方の変化といった構造的要因があることは否定できません。
ただし、より本質的な問題は、自治会運営の仕組みや行政としてのサポート体制が時代の変化に十分に対応できていない点にあると感じています。
もちろんこれまで何度も確認してきたとおり、自治会はあくまで独立した自主組織であり、行政が上から介入するようなことがあってはなりません。
しかし、同時に、行政も協力をお願いしている立場であることも事実です。
ここまでの質疑で、自治会は市民生活と行政の橋渡しをも担う大変重要な存在である一方、役員の成り手不足や高齢化、各種業務の負担、情報発信の課題など、現場の悩みが幾つも浮き彫りになったと思います。
これらの課題に対して、独立性の尊重を前提としつつも、行政としてどのような支援が可能なのかをゼロベースで再検討する必要があるのではないでしょうか。

その前提のもとで、個人的な提言も含めまして、この項目の最後である(4)番の今後の取組に入らせていただきます。
市としての効果的なフォローを考える上では、何よりもまず市内の各自治会の実態をもう少し細かく分析する必要があるかと思います。
本市の強みとも考えられる区長会の枠組みを活用して、各自治会の運営状況に関する詳細な実態調査を実施してはどうかと考えます。
この点についてどのようなご認識か伺います。
三浦市区長会では、各区の総会や役員会、防犯活動、交通安全活動など、活動内容に関する調査は年に1回実施してきましたが、各自治会の運営方法につきましては、各自治会の実情に応じて対応していただいており、これまで特に運営状況に関する実態調査を行っておりません。
ただ、一部の区長から、他の区の運営状況を知りたいという声が上がることもございます。運営状況を把握して各区で共有する必要性などが高まれば、調査の実施について区長会として検討することになると考えております。
確かに現状の職員体制を考えると、行政主導ですぐに調査や分析を実施するのはなかなかの厳しさがあるということは重々承知しております。
しかし、今の答弁にもあったように、自治会の役員さんが新たな取組を検討する際にまず気になるのは、他の自治会はどうしているのかという点です。
これは、私たち議会や行政が政策立案の際にまずほかの自治体の事例を参照することと同じであり、自治体間の相互参照の重要性については職員の皆さんも実感されていると思います。
そうすることで、現時点で未実施の施策に取り組む大義が生まれてくるわけです。
今のところ、そうした情報を集約・共有できる仕組みがなく、市としても情報提供の支援のしようがないというジレンマがあるのではないでしょうか。
調査の主体をどこに置くかは検討が必要ですが、正確な状況把握なくしては有効な支援施策も生まれません。
改めて実態調査の実施を要望いたします。
もう1点、自治会の持続可能性を高めていくには、若年層や転入者が参加しやすい環境づくりが不可欠です。
そのためには、SNSやホームページ、イベントなどを活用した柔軟な関わり方を提案していく必要があります。
先ほど触れた54区の写真展もその好例だったと思います。
市として今後そのような取組を検討しているのか伺います。
若年層や転入者に対する各区の接点の強化につきましては、各区によってさまざまな課題や実情があり、取組状況も異なるものと認識しております。
区長会事務局として、各区の対応について区ごとに取組を支援していくことは難しいと考えております。
一方で、現在、令和5年度にリニューアルした区長会ホームページにつきましては、活用方法を検討していると伺っており、状況が整えば、区長会ホームページを各区の広報や情報発信などに活用することが可能になると考えております。
若年層や移住者の参加を促すためには、入り口としての情報発信だけではなく、定例会の運用やその他の業務の見直しなど、自治会内部の在り方そのものを見直す必要もあるかと思います。
とはいえ、各区ごとにゼロから個別に最適化するのではなく、共通の仕組みや支援の形があってもいいと考えます。
先ほども挙げたように、ホームページの活用はその第一歩になり得ると思います。
情報発信の手段としてだけではなく、内部の業務にもITを活用することで、役員の負担軽減や世代交代のきっかけにつながる可能性があります。
もともとベッドタウンとしても栄えた本市ですから、長年IT企業にお勤めになり、今なおスキルを生かしたいと考えている高齢者の方も少なくないと思います。
むしろIT化推進が自治会に参加する機会のなかった方々を取り込むチャンスにもなり得ます。
ぜひ、せっかく立ち上げた区長会のホームページを起点に、さらなる活用方法を模索していただきたいと思います。
さて、今、ホームページの活用という話が出ましたが、自治会における役員の負担軽減や若年層の参加促進という観点からも、自治会におけるIT推進、ICT推進は、もはや不可欠だと言っても差し支えないかなと思います。
情報の回覧のスピード向上、要望や委任などの意見集約の簡略化、紙媒体による印刷コストの削減、災害時の安否確認、会費等の集金の電子決済など、IT促進が自治会運営に寄与する可能性は計り知れません。
こうした実情を踏まえ、自治会のIT推進について、市として支援の枠組みを検討したことがあるのか伺います。
各区の運営内容につきましては、各区の実情に応じて対応していただいており、これまでに市として区の運営のIT化推進について支援の枠組みを検討したことはございません。
最近になって会費徴収に関するアプリの紹介などが事業者から届くことがあり、そのような情報を集約して、区長会事務局として各区に提供していくことは可能だと考えております。
やはりここについても自治会の自主性を尊重する方針から、これまで具体的な支援には踏み込んでこなかったということかと思います。
しかし、今やITの力を活用していかなければ、自治会の機能自体が維持できなくなるリスクすらあります。既に民間では、自治会のこうした課題に対するサービスも登場し始めています。
ぜひそうした情報を積極的に提供していく姿勢を取っていただきたいと思います。
そして、情報を渡すだけではなくて、導入に向けた予算措置としての支援も検討していただきたいと思います。
もちろん恒常的な予算措置を求めるものではありません。
過剰な関与は自治会の自主性を損なうことにもなりかねません。
ただし、例えば実証実験的な導入に対する一部補助など、新しい取組に動き出すためのモチベーションにつながる支援の形は十分に検討されるべきものではないでしょうか。
既に引用しましたが、令和4年に総務省が公表した自治会等に関する市町村の取組調査によると、自治会のデジタル化に既に支援を行っている自治体は7.6%。
さらに、今後支援を予定している自治体も7.6%となっており、全国で1割以上の自治体が何らかの支援に動き出しているという状況です。
今後はこの数字がさらに増加することが見込まれます。
本市としても、高い加入率に安住するのではなく、次の世代の地域コミュニティ形成につながる支援の仕組みづくりに本腰を入れて取り組むべきだと考えます。
とはいえ、本市の厳しい財政状況では、このテーマを予算確保の最優先に持っていくことの困難さも承知しています。
そこで、財源確保の観点からは、例えば休眠預金等活用制度のような外部資金の活用も視野に入れるべきです。
この制度は、行政では対応が難しい社会課題の解決に向け、こども・若者支援、生活困窮者支援、地域活性化支援などの分野で活用ができる仕組みです。
令和5年度には法改正も行われ、支援の幅も広がってきています。
こうした制度を市が積極的に周知し、伴走型で申請を支援するという形で自治会のIT化支援につなげることも可能ではないでしょうか。
また、既に一部の自治体では、自治体の責務として、自治会の負担軽減を明記した条例を制定している事例もあります。
議員提案により生まれた条例であり、自治会の役割、市の支援の必要性を明文化し、自治会の過度な負担を避けるための配慮義務を設けているケースです。
私自身も、こうした自治会支援に関する先進事例を引き続き研究しながら、現実的な目線で提言を行ってまいりたいと思います。
行政としても、自治会運営の持続可能性という本質的な課題に、真摯に向き合っていただくことを望みます。
もはや行政の自治会への関わりは、自主性の尊重という言葉だけでは立ち行かない段階に来ているのではないでしょうか。
限られた人員配置の中で、目立たないところでも支援に尽力されている職員の皆さんには深く敬意を表しつつも、今後さらなる一歩を踏み出していただくよう、強く要望をさせていただきます。
以上でこのテーマに関する質問を終わります。
新市長の公約と認識について

それでは、2番目のテーマである『新市長の公約と認識について』に入りたいと思います。
順序が少し逆転してしまいましたが、改めて、出口市長、このたびはご当選、誠におめでとうございます。
今回選挙が行われたことによって、さまざまな民意が確認できました。
それ自体は三浦市にとって大きな価値であったと思いますし、私も一政治家として大変勉強になりました。
思うところはいろいろありますが、とにかくこの一般質問という公の場において、議員として市長の認識を正しく把握する義務があると感じておりますので、諸々の事実関係をお伺いします。
率直なお気持ちをご答弁いただければ幸いです。
まず初めに、少し大きなテーマですが、今回の市長選で表明された民意について、出口市長がどう受け止められているのかということです。
先の市長選挙では、出口市長が7,782票、吉田前市長が6,562票、秋葉候補が768票をそれぞれ獲得しました。
個人的にはこれらの全ての得票が民意の現れであると考えていますが、この結果について、当選時の高揚したお気持ちではなくて、今、市長という役職に就かれてどう感じているかを伺わせてください。
その選挙結果についてどう感じているかということなんですけど、大きく述べますと、やはり三浦市に住んでいる三浦市民の皆さんが変化を求めていたと。
これまでの20年間、やはり閉塞感を感じていらっしゃった方が多く、今後の三浦市の将来を考えて新しい一歩を踏み出さなきゃいけない、そのように感じていらっしゃる方が多く、その結果として選挙結果があるというふうに感じております。
ちょっと誘導尋問になってしまいますけれども、当然、出口市長に投じられた有権者だけではなくて、吉田前市長、秋葉候補に投じた方もいるわけですけれども、それらも民意だと受け止めているという認識でよろしいですか。
もちろんご指摘のとおり、私にご投票いただいた方だけでなく、吉田前市長、そして秋葉候補に投票された方、それぞれもちろん民意ですし、投票に行かれなかった方、この皆様については票という形では民意は示されてはいませんけど、当然その方々もそれぞれ三浦市に住んで考えることがある、感じることがあるわけですから、そういったこともしっかり拾えるように、今後活動していきたいというふうに考えています。
その認識が確認をできて安心をしました。
今、一部ネットやSNSではその民意の対立をあおるような投稿も見られますが、市長という本市のかじ取りを担うたった1人のリーダーという立場である出口市長は、今申し上げたとおり、ご自身に投じられた得票だけではなくて、他の候補者に投じられた票に対しても、それぞれに有権者の切実な願いがあると。
そこに思いをはせる責務があるはずです。
もちろん選挙ですから当選人と落選人が出ることは避けられません。
しかし、選挙で勝った多数派が少数派を弾圧するような構造というのは、民主主義の対極にあるものです。
そこについては、同じ見解であることが確認をできました。
さて、先の一般質問においても議論が交わされていた部分ですけれども、まず、社会福祉協議会に関する投稿についてです。あの投稿を初めて見たとき、私は正直、心底驚きました。
一社会福祉法人に対して人事的な圧力をかけるような極めて不適切とも取れる内容であることはもちろん、これまでの主張や投稿との連続性や一貫性が感じられず、非常に唐突な印象を受けたからです。
また、投稿後の対応についても、率直に申し上げて納得のいくものではありませんでした。
できる限り先日のやり取りとは重複を避けながら、事実確認と認識の整理のために質問をさせていただきます。
先日、11番議員の質問に対する答弁の中で、本動画の投稿については、登庁後に職員と議論をして削除した旨の発言がありました。
出口市長の初登庁日が6月30日と承知しておりますので、削除したのはそれ以降になるかと思いますが、具体的にいつ投稿を削除したのかお聞かせください。
すいません、記憶で申し上げるのでもしかしたら不正確かもしれませんが、8日だったと記憶しています。
記憶では7月8日だということですね。結構最近の話というところですね。
そもそもこちらの投稿がSNS上で行われたのは市長選の告示日であったと記憶をしていますが、この投稿を受けて、社会福祉協議会からは抗議文が出されていたと聞き及んでおります。
私自身、投稿のコメント欄でその存在を確認しています。
この抗議文の内容について、市長ご自身は当初から確認をしていたという認識でよろしいでしょうか。
抗議文は私の自宅に郵送で送られてきておりますので、そこでしっかり確認させていただきます。
その抗議文を見て、投稿内容に問題があるという認識は持たれなかったのでしょうか、伺います。
誤解を生じるような内容が結果的にあったというふうには感じました。
誤解を生じさせる認識はあったけれども、何も対応しなかったということなのかなと思います。
先の答弁で、市長ご本人が同協議会を三浦市の福祉サービスの重要な業務を担う組織であると評価する旨の発言がありました。
そんな重要な事業者からの抗議文に何の問題意識も持たず、その時点でなぜ謝罪や訂正、動画の削除を検討しなかったのか、改めてお聞かせください。
一度公に発した発言でございますので、訂正もしくは謝罪させていただくにおいても、しっかりとその内容について精査して、精査した自分の自己認識及びそれぞれの状況をよく把握した上で発言をする、そのことが必要だと。
そして、その精査に少し時間がかかってしまったというのが現実でございます。
反省はしていたけれども、行動に移すことができなかったというところなのかなと思います。
先の答弁で、あの動画の投稿は一般論として申し上げたという趣旨の論理のこじつけには正直全く納得感がありませんが、誤解を生じさせる適切でない内容であったと判断し、動画を削除することを決めたということでした。
先の答弁において、関係の方々にご不安やご心配をおかけしたということに対してお詫びをしていますが、私は謝罪するポイントがずれていると思っています。
不安や心配を与えたというだけではなくて、明確に社会福祉協議会の社会的信用を損ない、重大な損失を与えたとも考えられます。
繰り返しますが、先日の答弁の中で、社会福祉協議会が三浦市の福祉サービスの重要な業務を担う組織であるということを述べていることと、そんな組織に対してあのような挑発とも取れる投稿を行ったことの整合性が全く取れないんですね。
同協議会の社会的信用を損なう結果となったのではないかという私の認識について、率直にどう思われますか。
あくまでそのハラスメント等々があるかどうか……。
あるかどうかということで、一般論として申し上げました。
そのため、あの投稿によって社会福祉協議会の信用等々を失墜させたという認識はございません。
認識はないというところですね。
そこは、じゃあ、これから精査が必要だと思います。
先日からの答弁で、市長、行政の答弁と言っていいんですかね、私人としての責任という、公職に就任前の私人としての責任という言葉を何度か使われていたかと思います。
ここで、今後の議論の関わる全体的な整理となりますが、そういったこの私人としての責任というところに関して、先日の一般質問の中では、市長就任前の私人としての責任と就任後の公職者としての責任という二項対立の軸で、そこだけで語られたように思います。
一般論として申し上げますけれども、例えば、仮にとある自治体で市長就任前の身勝手な言動によって損害賠償を伴うような訴訟が提訴されたと仮定します。
それを公職者の責任として位置づけて、公費で裁判費用や賠償費用を支出するなどということは決して許されるべきではないと当然のことながら思います。
ですから、行政として、特に今回の一件について、あくまで私人としての出口市長の問題であり、公職者としての責任とは認められないという姿勢を示すということには一定の理解はできるかなと思います。
しかしながら、私はこの二項対立の構造、私人か公人かだけでは整理し切れない部分があると考えています。
それが政治家としての道義的責任という第三のレイヤーです。
出口市長は当時、まだ就任前だったとはいえ、市長選挙に立候補され、政治的主張を明確に掲げていたわけです。
その見解や姿勢を信じて実際に票を投じた有権者が大半だと思います。
法令的には私人かもしれませんが、政治家として有権者の信託を得ようとしていた以上、その言動には明確な責任が伴うと考えるのが自然です。
私はこの政治家としての道義的責任というのは、立候補を表明した瞬間から生じるものであると考えています。
にもかかわらず、それをあたかも選挙とは無関係の私人の発信として処理しようとする姿勢には違和感を拭えませんでした。
この点についての整理が前回の答弁では明確に示されていないと感じたため、あえてここで明確に示させていただきました。
私が今回最も重視して問いかけたいのは、この政治家としての道義的責任に対する出口市長ご自身の認識です。
立候補表明以降のご自身の言動について、それを単なる私人として捉えているのか、それとも政治家としての道義的責任ある個人として捉えているのか、市長としての率直な思いを聞かせてください。
指摘の点については、立候補表明以降、政治活動として活動させていただいていますので、政治家としての当然側面があると。
その部分でも未熟な部分があった、誤解を生じる部分があったことについては、おわび申し上げたいと思っています。
今、謝罪でなくて事実確認を求めているわけですけれども、政治家としての道義的責任は感じているというところになるかなと思います。
その認識は確認できてよかったです。
ここを前提にして、個別具体の質問を展開していきたいと思います。
続いて、旧三崎中学校跡地、城山地区の売却に関する投稿について話をさせていただきます。
先の一般質問に対する答弁を受けて、幾つか不明確な部分がありましたので、改めてお伺いさせていただきます。
先日の答弁で、当該地区が10億円で売却できたはずだという疑義、問題意識については、解消された旨の発言がありました。
まず、この疑義が解消されたのはいつのことなのでしょうか、伺います。
10億円での価値があるというふうな旨、発言させていただいています。
ご質問の件については、登庁後、職員と鑑定書等々、過去の議事含めて改めて確認させていただいて認識を持ちました。
登庁後のタイミングということで、その時点で投稿内容に誤りがあったことに対する訂正や謝罪は何らかの形で行われたんでしょうか、伺います。
現時点では、SNS上で修正等々はまだしておりません。
SNS上でと限定されましたけれども、ほかの媒体で何かされたのでしょうか。
今議会においてしっかりご説明させていただいていくということをまずやらせていただいています。
その上で、SNSにおける投稿、これについて訂正ということをしていきたいというふうに考えております。
この議会がその訂正の場というふうに認識されたということですね。
11番議員による質問においても、10億円で売却できるとの市長のご発言や算定の根拠が事実誤認に基づくものであることが明らかになりました。
にもかかわらず、その時点から今既に中3日が経過した現在に至っても、当該SNSについて、この議場以外の場で訂正や謝罪がないまま残り続けています。
この対応について、市長ご自身の誠実さを疑われても仕方ない行為かなと思いますが、改めて、なぜこの明確な対応を取らなかったのか、その不作為の理由をお聞かせください。
繰返しになりますが、SNSでのその投稿はまず削除するということはせず、このような公の場での説明とおわびをさせていただいた上で、今後、速やかに必要な説明などを加えつつ、削除、閲覧できるような手当てをしていきたい、それが最も適切な対応であるというふうに認識しております。
そこは市民の皆さんに判断いただくところですけれども、そのようなお考えだというところです。
さて、先の答弁において、正当な手続きの上で確認された土地評価額について、市長は議事録の該当部分を“見落としていた”と述べられておりました。
この説明を前提にすれば、令和5年12月8日に開催された総務経済常任委員会の議事録については、投稿当時、既に確認していたということになるかなと思います。
であれば、なぜ最も重要であるはずの鑑定評価額の記載部分だけを見落としたのか、ここについては大きな疑問が残りますけれども、いずれにせよ、当該委員会の議事録を投稿前に確認していたという認識でよいのか、改めてはっきりとご答弁ください。
議事録を確認したのは間違いないんですけど、当時どの議事録を見ていたのかというのはメモしておらず、その売却額の確認は、2億4,000万円ですかね、確認をしたということは記憶していますが、それ以外については細かく記憶がないというのが現状でございまして、鑑定額3億数千万円というのは見ていないというふうに認識しております。
議事録をご覧になったことがあると思うので分かると思うんですが、デフォルトで議事録の検索画面ではこの本会議の答弁にチェックがついているんですけれども、当該の委員会のものを検索しようとすると、自分の意思でちゃんとクリックをしないとできないような一応デフォルトの構造になっていますけれども。
今の答弁をお聞きして、もしかすると本会議の議案説明だけを見て、総務経済常任委員会の質疑、答弁に関する議事録を見ていなかったのかなというふうな印象も受けたんですけれども、その常任委員会の議事録を見たのかどうかというところに関しては、記憶いかがですかね。
申し訳ないんですけど、議事録のどこを見たのかというのははっきり記憶がないです。
売却額のほうは確認させていただいて、それが委員会なのか本会議なのかというのはちょっと記憶がないです。
当該投稿に寄せられたコメント欄においてですけれども、『なぜ議会がこの売却を承認したのか』という問いかけに対して、市長ご自身が『私もそれが不思議です』と回答されていたことを確認しています。
あえてもう一度聞きますけれども、常任委員会の議事録、ちゃんと見ていたんでしょうか。
繰返しになります。
どの議事録を見たのかメモしているわけではないので、はっきり申し上げることはできないです。
そうすると、先の11番議員への答弁で述べられていた“見落とした”という言い方、ここに関しては、かなり不誠実な答弁だったのかなという風に思います。
そういった不誠実さで答弁することはちょっとお控えいただきたいと思います。
もう1点、SNS上で、これもその投稿上でですけれども、鑑定評価を取っているが、それ自体に問題があるかもしれないという旨のコメントに対して、市長ご本人が、詳細を調査する必要があると述べられています。
ちなみに、もともとの投稿文にはこんな記事が掲載されています。
「旧三崎中学校跡地は、土地の市場価格が最低でも10億円程度の価値がありましたが、2億4,000万円で売却しています。また、情報公開が不十分なため、状況は不透明なままです。皆さんに現状を知っていただくことが大切だと考えています」
このように行政の情報公開が不十分であると断定していますけれども、そもそも本件について、情報公開制度を活用して何らかの情報公開請求を行ったのか、事実確認をさせてください。
行っていません。
情報公開請求を行って、その開示状況に不満があるというなら話が分かります。
しかし、そもそも情報公開の請求すら行っていないのにもかかわらず、情報公開が不十分であると断言する根拠は何だったのでしょうか。
請求すら行っていない状態で不透明だと市民に印象づけるような投稿をすることは、事実誤認、事実確認の検証や裏取りを怠った意図的なミスリードだとしか思えません。
この点についてどう思いますか。
意図的にミスリードしたということはありませんが、情報確認が不足していたということは、先日の答弁のとおり、皆様にその誤解を与えてしまった、そのことについてはおわび申し上げたいというふうに考えています。
やはりその事実確認、政策・公約の裏取りの努力が不足していたのは明らかだと思っています。
今この10億円の問題に絞って質問を展開しましたけれども、この点に限らず、市長が公約や政策を考えるための現状把握として、過去の議事録というものをどうやって活用していたのか知りたいんですね。
例えば、本会議、各種常任委員会については、期間を決めて全部目を通したとか、それとも検索を使って必要な情報だけをピックアップしたのかなど、全般的な議事録との向かい方についてお聞かせいただけますか。
網羅的に例えば3年読んだとか、そういうことはありません。
自分が調べたいということに対してその検索をかけて、読んだということでございます。
やはり市長候補、今、市長ですけれども、として、少なくとも主要な議論については体系的に把握しようとする努力があってしかるべきだったと私は考えています。
政治経験がなくてもいいと思います。
それ自体が1つの価値でもあるとすら思っています。
しかし、それは知識や経験の不足を補うだけの努力があって初めて意味を持つものだと思います。
私は市長の公約やSNSの投稿から、その部分が著しく欠如していると当時から強く感じていました。
そして、今の一連の答弁で、残念ながらその認識はますます強まりました。
市民の声を聞く。
その姿勢や行為自体は本当にすばらしいことだと思います。
私もたったの2年ではありますが、私なりに市民の方との対話を重視して、試行錯誤を繰り返しながら取り組んでまいりました。
出口市長のフットワークを駆使した政治活動を見て、私もいい意味で刺激を頂いたことは事実です。
しかし、政治家としての対話が有意義なものになる前提には、市政に対する正しい情報を把握しようとする努力、これが求められると思います。
むしろその努力こそが、対話をする市民に対する本当の意味での誠意ではないでしょうか。
この指摘について、率直にどう考えられますか。
正当な指摘だと思います。
今回多々足りてない部分があった。
その点についてはしっかり受け止めて、今後、市長という立場においてしっかり情報把握、正確な情報把握に努めて、正しい運営をしていきたいというふうに考えています。
特に今取り扱った社会福祉協議会、そして城山地区の売却に関する投稿は、その重大性から、この定例会だけで終わる話じゃないと考えています。
次の質問に行きます。
小中学校の統廃合計画の白紙化と学校教育ビジョンの見直しについてです。
まず前提として、教育委員会の決定事項に対して首長がこれを覆そうとする姿勢そのものについては、私は教育の中立性を損なうおそれがあると強く懸念しておりました。
ただ、この点は、先日の11番議員のご質問の中で一定の確認がなされたと受け止めておりますので、ここでは繰り返しません。
さて、その11番議員の質問において、市長は出馬会見の段階では今の学校を全て残すといった趣旨の発言をされていたものの、その検討を経て統廃合を進めていくことについて理解を深めたと答弁されました。
ちょっと少し曖昧で意図が分からなかったんですけれども、つまり当初の認識から一定の変化があったということだと理解をしています。
では、その理解が深まった時期、すなわち統廃合計画の白紙撤回から転換したという風に印象を持っていますけれども、それはいつ頃だったのかお伺いします。
今現時点で、ごめんなさい、ご質問にお答えすると、全ての小中学校残すと会見で、これ、三崎小学校のところを念頭に申し上げたんだと思いますが、その後、集会等々で市民の皆さんと交流する中で、やはり複式になったり、学校のクラスが5名ですとか10名を切って少なくなっていく、そして複式になっていく。
そうなることに対しては一定の方々がやはり懸念されていた。
やっぱり社会性を養うという観点で懸念されていた。
そういったご意見も踏まえて、そして、その意見を踏まえた上で学校教育ビジョンのアンケートを改めて確認させていただいたときに、アンケートでも、学校統廃合については、やはり複式になったときに検討を開始する、それに対する賛同が多いということを踏まえて認識が変わっていった、深まっていったというふうな経緯でございます。
これ、選挙期間中のビラなんですけれども、ここにも小中学校の統廃合計画を白紙に戻すと書いているんです。
今お話しいただいていたその転換点というのは、ここに白紙化と記載しているわけですから、このビラを出した後の話ということでよろしいですか。
その前の話で、そこのあのビラに載っているのは、その根幹である1中学校区1小学校、そういった根幹のところで念頭に置いていると。
そういった意味ではその内容のとおりでございます。
そうですか。
そうですね。
今ご答弁でもありましたけれども、複式学級になってクラスが少なくなり、社会性を営むのが困難になった場合において統廃合を進めることについて理解を深めたと。
これ、先日の答弁でも述べられていました。
このロジック自体が、実は現行の学校教育ビジョンと全く同じことが書かれているんです。
具体的には、当該ビジョンには、小学校について、「現在の学校配置を維持しつつ、『複式学級』の設置が想定される状況になったときには、適正化に向けた検討を行う」と明記されています。
つまり、複式学級の発生というのを1つの契機として適正化を検討するという考え方そのものは、教育委員会として既にビジョンで明確に打ち出しているものなんです。
私自身、選挙中にこの市長の公約に「教育ビジョンの見直し」という文言があって、これを見たときに、当時その中立性への介入という懸念は一旦棚上げして、少なくとも複式学級であっても存続を検討する方向にかじを切るのかなという解釈をしました。
教育ビジョンを読み込んだことのある方であれば、同様の解釈をされた方も少なくなかった、大半だったと思います。
ところが、現時点で市長が示している考え方は、結局、複式学級の発生をトリガーにして適正化を検討すると。
現行の教育ビジョンと全く同じ内容であります。
そこで伺いますけれども、市長はこの学校教育ビジョンの何に問題意識を持ち、何をどう変えたいと考えて見直しや白紙化という強い言葉を使って公約に掲げたのか。改めて具体的にご説明ください。
先日来ご答弁させていただいていますけど、私の問題意識のコアにあるところは、そのビジョンの前提として1中学校区1小学校、これがうたわれていることです。
これについて、これまでの議論、長い年月にわたる議論があり、当時吉田前市長、4年前にその見直しも明言されている。
また、市民の皆さんからも、やはり1中学校区1小学校に対しては大きな懸念を持たれている。
私自身もそのように考えています。
そこについて最も問題意識を持っております。
これについてぜひ議論をしていきたいというふうに考えております。
教育ビジョンの読み込みのタイミングも含めて、ちょっ
と今の答弁を聞いていても正しい認識、あとは、何よりもこの文言を見た有権者に対して、その意図がちゃんと明確に伝わってない可能性は大いにあったんじゃないかなというふうに思います。
ちょっとここで終わります。
休憩
午前中に引き続き、続きの質問をさせていただきます。
ちょっと最後中途半端になってしまいましたけれども、出口市長の教育ビジョンの見直しと、この選挙でも掲げられていた学校教育ビジョン見直しというところの内容を確認すると、要は1中学校区1小学校というところの見直しというか、そこの慎重な精査が必要なんじゃないかというところのご意見だというところは把握いたしました。
この市長のご見解に関して、教育長、どう思われているかお伺いします。
まず、1中学校区1小学校ということが前提として教育ビジョンが策定されているものではございません。
ビジョンにつきましては、平成20年度、適正配置・適正規模の基本方針というものが策定されておりますけれども、それにのっとって進められているということになります。
その基本方針には、小学校の場合には、複式学級が見込まれる、そういう状況になったときに統廃合について検討いたしますというふうな書かれ方をしているわけなんですが、平成20年度以降、やはり子供の数が急速に減少してきているというふうなことで、市内の各小学校での小規模化ということも大分見られるようになってきた。
そうした中では保護者の不安ということも多く出てきまして、保護者同士の中で、子供の数が少なくなってきたのであの学校とあの学校を統合するんじゃないかというふうな噂というんですかね、そういう話も多く出るようなりました。
そういう状況を考えたときに、やはりこの先の三浦の教育を考えたときには、そういう数の理論ではなくて、やはり教育をいかに充実させていくのか、そして質をいかに向上させていくのかということをやはりきちんと考えなければいけないだろうということで策定されたのが学校教育ビジョンであります。
教育の充実、そして質を向上するということを、少子化という現実を踏まえながら考えていくということでのビジョンの内容になっているわけなんですが、それぞれいろいろ書かれていますので、ここで詳しくはお話し申し上げませんけれども、いろんな手だてを取りながら、中学校、小学校の連携を深めていきながら、子供たちのストレスも減らしながら、より9年間というものの教育を効果的に進めるにはというようなことなども示しながら、そうしたことを考え合わせていったときに1中学校区1小学校が望ましいであろうというような書かれ方をしているわけです。
ですから、まず、その1中学校区1小学校を前提にというふうなことについては、そういうふうな考えではないということをまず申し上げたいと思います。
今ご答弁があったように、1中学校区1小学校というのは、あくまで最終的にそうなり得るという話であって、別にそれ自体が目的ではないというところですね。
今の教育長のご答弁の内容も教育ビジョンにはしっかりと明記はされています。
ちゃんとそれを読んだんですか、なんていうことは聞きませんけれども、しっかりと出口市長も学校教育ビジョンを読み込んで精査を重ねた上で、その方向性というものを検討していただきたいなというふうに思います。
もう一つ、教育の公約として、探究型学習のモデル校、いわゆる学びの多様化学校を新たに設立というものがあります。
私もちょっといろいろ勉強させていただきましたが、ちょっと分からないのがこの統廃合計画との整合性です。
モデル校を新たに設立というところで、学校の数を集約していく統廃合の流れというところには矛盾するとも言えるのかなと思いますけれども、ここについて、先日の答弁の中では、既存教育の仕組みができないことができるようになるというような考え方は分かりました。
そこで改めて確認をしたいのですが、このモデル校の新設というのは、既存の学校を段階的にモデル校へ転換していくという構想なのか、それとも物理的に新しい学校をゼロから設立する構想なのか、その基本構想についてお考えをお聞かせください。
私の公約に掲げているモデル校の新設については、新しい学校を新設すると。
ただ、物理的にという意味では、既存の設備等々を使って有効活用すべきというふうな考えでございます。
そうすると、今後、統廃合をしたいわゆる廃校となった学校を活用する可能性、可能性というか、そういったことも構想としてあるという認識で間違いないですか。
そういった選択肢もありますし、既存の学校の空き教室が使えるのであればそちらを使わせていただくなど、幾つかの選択肢あると思いますので、そのあたりはもうこれから議論すべき点かなというふうに考えています。
ちょっとまた教育長にお伺いしたいんですけど、この学びの多様化学校を三浦に新しく新設するということについて、教育長としてはどのようなお考えかというところを伺います。
まず、学びの多様化学校についてでございますけれども、学びの多様化学校については、不登校の子を対象にした学校、これ、市長もお話をしているところなんですが、であります。
不登校のこどもたちというのはいろんな要因、段階があります。
学びの多様化学校に通える子、県内でも学びの多様化学校を設立しているところはあるわけなんですが、その学びの多様化学校に通う子供、通えるこどもというのはどういうこどもかと申し上げますと、不登校である状況であるけれども、その中で学びへの意欲ですとか、あと、学校生活への意欲が出始めた子、自分の学校ではないけれどもそういう学べるところに行きたいという意欲のある子が対象になります。
三浦市の現在の不登校の数というのは小学校で28名、中学校で50名、ちょっとまだ非公開のところがありますので約というふうなことで取っていただけるとありがたいんですけども、そういう数がおります。
先ほど申し上げたように、不登校の子にも段階があるんですね。
その段階があるということで考えていくと、現在、三浦市には、不登校の子供の対象の施設としては教育相談室というのがあります。
そこに通っている今の状況でいいますと、これ、小中合わせて、先ほど申し上げた小学校約28名、中学校50名ということの中で、週4日通えている子が2人、週3回通えている子が1名、週1回通えている子が4名の7名であります。
そういうことから考えていきますと、学びの多様化学校については、三浦市の必要性ということからすると、現時点ではそういう学校ではなくて別の対応、今、相談指導教室がありますけれども、そういうところを充実させていくというふうな考えが、三浦市の今の現状の中では適当ではなかろうかというふうに感じるところであります。
今の答弁をお聞きすると、両者のご見解は少しというか、ギャップがあるのかなというところを思いますので、そこはこれから議論を重ねていく、学んでいくところなのかなというふうに理解をいたしました。
私も学校を統廃合しなくて済むのであれば、それに越したことはないと本当に思います。
今年の3月、剣崎小学校が、116年の歴史に幕を閉じて閉校を迎えました。
この閉校に際して、1年以上、準備の段階からいろいろと関わらせていただきましたが、その中で学校という存在がいかにその地域にとって精神的な支柱であったか、地域の絆を形づくる象徴であったかというところを肌で実感し、何度も胸が詰まる思いでした。
しかし、一方で、こどもの教育環境を最優先に考えたとき、統廃合という判断がやむを得ない局面もあるということも私は理解をしています。
そして、その現実を見据えた上で、15年以上にわたる議論の集大成として策定されたのが学校教育ビジョンあるわけです。
市長がどのような思いとどのような検証に基づいてこの学校教育ビジョンの見直しや統廃合計画白紙化を公約に掲げたのか。いろんな変化があったことは確認しましたけれども、正直そこにまだ納得感が十分に得られていないう印象ですけれども、ちょっと時間の関係もありますので、今日のところはここにとどめたいと思います。
引き続き、教育の在り方については議論を続けさせていただきたいと思います。
もう一つ教育に関してなんですけれども、学校給食の無償化についてです。
先日の一般質問でも触れられていましたが、学校給食の無償化については、出口市長の公約であると同時に、前吉田市長の公約でもありました。
この政策については、子育て支援の強化という観点からも、また、税の配分の公平性といった観点からも、一定の合理性があると私も思っています。
ですから、実現すれば、市民にとって非常に喜ばしいことだと考えています。
そもそも本市ではこれまで給食費の半額免除が実現されてきましたが、これは前吉田市長が子育て支援を重要政策と位置づけ、都度、国から下りてくる交付金を学校給食に優先的に配分してきたという経緯があったからこそ成り立っていたものでした。
この点については、出口市長も十分ご存じのはずです。
しかし、この無償化を全額市の単独財源でやるには、財源的な問題としてなかなか大変なことです。
私はてっきり昨年の3党合意の内容も含めて、国の制度として無償化が図られる見通しを前提にした公約であろうと、そう受け止めていました。
ところが、先日の6番議員への答弁を拝見する限りでは、たとえ国の制度としての財源措置が整わなかったとしても、三浦市独自で無償化に踏み切る意思があると、そういった部分を受け取れる内容だったのかなと思っています。
この点について改めて確認させていただきたいのですが、現時点で市の単独財源によってでも無償化を実現する、そういった認識で間違いないのか確認させてください。
当然国の補助があるということが一番望ましいことですけど、それがなかった場合については、その実現に向けて検討を進めていくということです。
そういうことなのであれば、そこに意固地になり過ぎず、ぜひ国による財源化が確定してからの予算計上としていただきたいということを要望として上げさせていただきます。
これから市長としてさまざまな政策の実行に向き合っていく中で直面することになろうと思いますが、当然ながら市の財源には限りがあります。
本来必要とされる行政サービスにしわ寄せが行き、市民生活が脅かされるようなことがあっては本末転倒です。
出口市長の真っすぐな思いですとか、こどもたちのために何かを変えたいという純粋な気持ちは十分に伝わってきますし、私も賛同するところです。
だからこそ、これからはぜひ国や県の財源をうまく活用するという強かさ、こちらを身につけていただきたいと思います。
給食費無償化に関する質問は以上です。
次に、子育て支援の部分ですけれども、隠れ待機児童解消というところで公約に挙げられています。
隠れ待機児童問題の解消ですね。
ここで言う隠れ待機児童という用語は保留児童という意味でよろしいのか、改めて確認させてください。
ご理解のとおりです。
私も当選以来、議員としてこのテーマを訴えてきておりまして、行政側も財源的な問題を何とかクリアしながら、保留児童の解消に懸命に取り組んでいただけていると自覚をしています。
出口市長はこの今の対応、行政としての施策についてどのような認識を持っているのか、改めて伺えますか。
この保留児童の対応につきましては、保育士の確保ですとか、3歳児までですかね、の一時預かり所の開設等々、これまで努力されているということは認識しております。
本当に現場の職員さん、頑張っていろんな施策を打ち出してくれているんですね。
そういったところは継続して、しっかりとこれからも拡充に努めていただきたいというふうに思います。
これまで私もずっと主張してきましたけれども、本市、子育て世代を誘致するためには、保育体制の拡充というのは絶対的に必要だと考えております。
これからもここは議論を重ねられたらと思っています。
続きまして、ちょっとまたSNSの投稿についてなんですけれども、一番最新の出口市長の投稿で、いわゆる政治スクールのセミナー誘致についての投稿がなされておりました。
出口市長、この市長就任後となると思うんですけれども、6月29日のSNS投稿において、「保坂展人政治スクール ONE DAY SUMMER」に登壇をすると告知を行っています。
もちろん公序良俗に反さないセミナーに登壇するかどうかというのは自由だとも思いますけれども、このセミナーへの参加を市長として、フォロワーである市民に呼びかけた意図、これが何なのかというところを伺えますか。
意図としては、政治に参加していただく、政治について意識を持っていただく、これは広く一般にやはり私はよいことだというふうに考えていますので、そういった趣旨で投稿させていただいています。
今の趣旨で行くと、このセミナーでは主にどんなことをお話しするつもりなのか伺えますか。
まだその具体的な内容については決めていませんが、当然今回の政治活動、選挙ですとか、もしくは、今は市長という立場ですので、その後、短いですけど市長就任後のこれまでの期間、そのあたりについてお話しさせていただくことになると思います。
このセミナー自体が有料という認識でよろしいでしょうか。
実費経費相当分が参加者に求められるということですね。
そういうことになると、仮にお金を支払ってそうした選挙もしくは市政の情報を話すということになりますと、本来税金によって支えられている情報というところを一部の市民に対して対価つきで先行して提供することになるわけでして、情報の公平性が損なわれないのかなというふうな思いはあります。
そもそも地方自治法では、住民の知る権利を前提として行政運営の説明責任が課されていると明記されています。
これ、第1条の2及び第2条の第14項ですけれども、こうした法の趣旨からしても、市政情報の有償提供とも捉えかねられない行為というのは、説明責任の在り方として不適切である可能性があるかなというふうに思うんですけれども、この点についてどのような認識をお持ちですか。
あくまで政務、政治活動として行っていることで、これについては、広く現在でもいろいろな全国各地で行われていることと相違ないというふうに考えております。
政務として行うことに対しては不適切だと考えておりません。
このセミナーに登壇することで市長自身への報酬というのは発生するんでしょうか、お聞かせください。
無償でやらせていただきます。
このセミナーの主催である保坂展人と元気印の会は、政治団体という認識でよろしいでしょうか。
ご認識のとおりです。
これ、ちょっとスクール生の募集みたいなところも何か見た感じだと兼ねているようなセミナーだと理解していますけれども。
講師料の支払いがないにしろ、いち政治団体による資金集め活動にも取られかねないこのイベントに現職の市長が加担していると思われかねない構造なのかなというふうに思うんですけれども、この点について問題認識というのは何かなかったのか伺います。
それは自民党さんに限らず広くやられていることで、特にそれについて問題だと考えておりません。
ちょっと自民党議員でないので分からないんですけれども。そういうこともあるという認識だというところですね。
これまでちょっと問題提起していた投稿とは異なって、今回の投稿は、これ、明確に市長に就任された後の投稿だと言えると思います。
いわば市長としての公人の立場も生まれる中で発信された内容であるというところが、ちょっとほかのところと違うのかなというふうに思っています。
市長は中立性が求められるというところの意味で、この投稿が本当に適切だったのか、リスクマネジメント、そういう疑義を持ちかねない投稿だったんじゃないかというところに関しては、今問題ないという認識だということでしたけれども、ちょっと今までの投稿の経緯も含めて、ぜひちょっと慎重に考えていただきたいというふうに思います。
これは要望としてお伝えしておきます。
最後の項目ですね。
最後ですけれども、ボーナス及び退職金の全額返上についての公約です。
まず前提として、出口市長の後援会ニュースであるこの二つ折りのビラですね。
こちらに、中を見ますと、「三浦市の衰退が続いても市長報酬は変わりません」との記載がありました。
これは一見すると、前任の吉田市長の任期中、市長報酬が一度も減額されたことがなかったかのような印象を与えかねない表現だと感じています。
出口市長は、前吉田市長の任期中に市長報酬が減額されたことがあるという点について、どのような認識をお持ちでしょうか。
私が調べたのは、そちらに載っている4期分ですかね、の金額を市役所のデータから算出というか、抽出したということで、実際にそれが何%の減額だったかについては認識していませんでしたが、支払いに変動があるということは、そちらに書いてあるとおり認識していました。
今ちょっとごめんなさい。聞きそびれちゃったら申し訳ないんですけれども、この4年間、5期目のこの4年間の市長報酬が変化がなかったというところだけを切り取ってここを載せたという認識でよろしいですか。
そちらにあるのは、ごめんなさい、4年分ですかね。そうですね。そこの、ごめんなさい、ボーナスの部分ですね。
期末手当のところ、変動があると思うんですけど、そこを今指してご説明させていただきました。
この書き方だと、上の説明で5期20年というところの説明をしておいて、その流れで見たときに、「三浦市の衰退が続いても市長報酬は変わりません」という、これ、構図なんですよ。
今お聞きすると、この4年間、もちろん退職金のところの変動はありますけども、この4年間変わっていませんよというグラフを補足するようにつけている構造になっています。
ちょっと担当課に聞きますけれども、実際、吉田前市長、この5期目の4年間というだけでなくて、全20年間の任期の中での話ですけれども、報酬等について独自の削減を行った実績があるのか伺えますか。
吉田前市長の在任期間中におきましては、給料月額や期末手当を減額した実績はございます。
削減の具体的な事例、幾つか挙げていただけますか。
幾つかの事例をお答えいたします。
平成22年4月1日から平成25年6月28日までの市長任期におきましては、厳しい財政状況を踏まえ、給料月額の20%減額を実施しております。
また、平成22年度の期末手当の役職加算についても凍結をしております。
給料月額の減額で年間約220万円、役職加算の凍結で年間約33万円の減額という計算になります。
この期間中におきまして、さらに給料月額の減額率を引き上げた期間もございます。
そのほか、平成25年6月28日、任期満了に伴う退職手当を20%減額しております。
平成25年6月29日から同年12月31日までの間における給料月額を30%、平成26年1月1日から同年3月31日までにつきましては、50%減額している事例がございます。
ちょっといきなり聞いたということもあって、多分計算式も相当複雑になると思うので、実際その任期中幾ら削減したのかというトータルの金額はちょっと確認が難しいかなと思いますけれども、今お聞きする限りだと、かなりの金額が、報酬が削減されていたのかなというふうに理解をしました。
改めて市長に聞きます。
出口市長にお聞きしますけれども、この事実、認識した上でこのビラを作ったという認識でよろしいですか。
一つ一つの減額の事例を認識して発言したわけではないです。
これも当然全部議案で出てきている事例なわけですよ。
だから、これも先ほどちょっと議論もありましたけれども、議事録をちゃんとつぶさに精査をすれば検証ができたはずのところです。
そうした事実があるにもかかわらず、私が一番問題に思っているのはこの紙面の構成ですね。
あたかも市長報酬が一度も削減されてこなかったかのような記載を行って市民に周知を行っていると。
ここは私はちょっとフェアな姿勢だとは言えないと思います。
どのような認識をお持ちですか、ここについて。
今申し上げたとおり、全てそういった過去の事例を把握して発言しているわけではありません。
よって、ミスリードがあったということについては反省したいです。
そこの認識は分かりました。
あと、そもそもなんですけれども、このように削減した、返上という言葉を使っていますけれども、お金を財源にして特定の政策領域に充当する旨の記載があります。
こうした使途の限定を伴う報酬の返上という声は、形式上、条例改正でやるというふうな答弁もありましたけれども、市長が自らの給与の一部を市民のために寄附するという行為にもなりかねない、なり得るわけで、特に選挙時の公約との関係性でいうと、公職選挙法上の寄附行為の誇張、いわゆる実質的な寄附です。
こちらに該当する可能性もあるのではないかなというふうに考えられますけれども、この点について、市長はどのような法的整理をされた上で公約に掲げたのか伺います。
寄附行為の禁止については承知しております。
この公約を掲げるに当たっては、自身のその判断のみならず、弁護士に相談して、条例改正を行った後それを減額するということについては問題ないということで確認して、発信させていただいています。
弁護士に確認をしたというところでした。
仮に条例改正によって報酬をカットする形式を取るというところだとしても、最終的にその是非を判断するのは議会、我々議会であります。
すなわち、議会の判断を伴う事項というのをあたかも確定事項であるかのように公約として掲げること、そして、議会に対する責任転嫁ですね。責任転嫁だと捉えかねないこの公約を掲げているというところも私は問題があるのかなと思いますけれども、そこについての認識はいかがですか。
責任転嫁をするというようなつもりは毛頭ありません。
公約の実施に関しては、責任は私自身にあって、関係する議決を頂けるように、しっかりと内容の構築等をしっかり丁寧にご説明させていただくということが私の責任であると考えております。
私は、我々の議員報酬も含めてですけれども、特別職の報酬というのは職責に対する対価であると考えています。
この旨は先日の答弁でもありましたけれども、その答弁の中で、学校の修繕などにお金を回すために報酬を削りたかったと。そのお気持ち自体、否定するつもりはありません。
ただ、これまで何度も確認してきたように、やはりこの出口市長は公約形成における現状分析、検証の姿勢というのがやはり甘い、そして怠慢があると言わざるを得ないと思います。
そうした不十分な、ある意味でずさん、かつ無責任な情報整理をしておきながら、このようなシンボリックな報酬の返上公約を掲げるということは、正直申し上げて耳障りのいい票集めであると、そういう批判も免れないのではないでしょうか。
本当に市政のかじ取りの責任を取るというのは、見せかけの自己犠牲ではなくて、徹底した現状把握と検証を重ね、最善の政策を実行するというその努力にこそ見いだされるものだと思っています。
少なくとも私はそう考えているんですけれども、この点について市長はどうお考えかお聞かせください。
公約自体は法律の問題はないことを確認しています。
また、グラウンドですとか学校施設の現状にやはり私としては大きな衝撃を受けて、そして、その財政が厳しいということは、もう本当に耳が皆さん痛くなるほど聞いている。
実際に厳しいと。
そういう中で私ができることは何だということを考え、その上で出した結論でございますので、耳触りのいい票集めには当たらないというふうに考えております。
時間もありますので質問はこの辺でやめますけれども、最後に改めて出口市長に申し上げさせてください。
一連の答弁を通じて、やはり出口市長の市長候補としての認識の甘さ、あとは対応の不誠実さ、これは否定できないレベルであることが確認できたのかなと思っています。
先の選挙において、当時の与党議員のみならず、野党議員も含めて全議員が、若くて、フレッシュで、人柄もよさそうな出口市長候補をなぜ表立って支援できなかったのか。
その意味をいま一度しっかりと考えていただきたいんです。
それは政局や議員の利害といった類いの話ではなくて、単純に出口市長の市長候補としての姿勢や資質に疑問符をつけざるを得なかったんだということなんだと思います。
これまで確認してきたとおり、出口市長は正しい情報の裏取りを怠り、その上でこれまでの市政運営を頭ごなしに否定をして、挙げ句の果てには、知ってか知らずか、事実を歪曲したまま市民を扇動するかのような投稿も行ってきました。
もしこれが全てを把握した上での意図的なものであったとすれば、本当に悪質だと思います。
その結果、出口市長の発信や公約を信じた有権者を裏切り、今やあなたの部下となった、現場で必死に奮闘してきた職員の思いまでも愚弄する形になっているのではないでしょうか。
責任と矜持を持って市政に携わってきた議員の立場から言わせていただければ、憤りすら感じたというのが正直なところです。
私は政党もイデオロギーも、地元民と移住者との垣根も越えて、オール三浦でこのまちをよりよくしていきたいと願っています。
だからこそ世論の分断をあおるかのような出口市長の戦い方には全く共感できなかったと、それが私の率直な思いです。
以上、そうしたこれまでの言動を深く反省すること、そして、今後、政治家としての道義的責任を果たすことを強く要望しまして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。